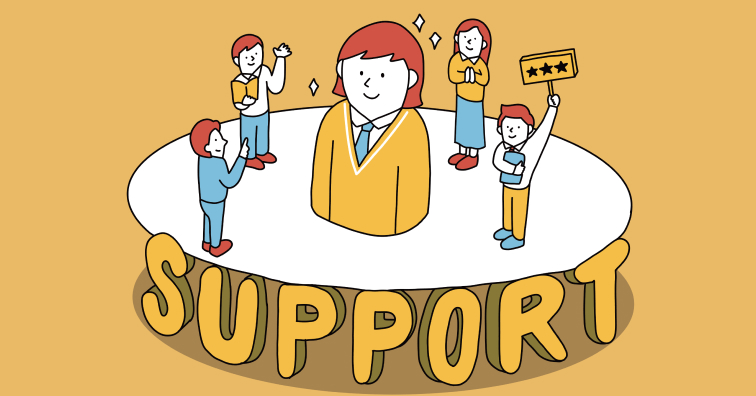特別支援学校とは?発達障害のある子どもに適した学校選びのポイントを解説
COLUMN

「うちの子は、特別支援学校に通った方がいいのだろうか?」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。特別支援学校は、障害のある子どもがその特性に応じた教育や支援を受けられる学校です。本記事では、発達障害のあるお子さまを持つ保護者の方向けに、特別支援学校の対象や学べる内容、入学までの流れ、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
特別支援学校の基本情報
特別支援学校は、心身に障害のある子どもが、その特性に応じた教育や生活支援を受けながら学ぶための学校です。発達障害のあるお子さまにとっても、学習や日常生活を安心して送ることができる環境として、進路選択の一つとして検討されています。
ここでは、特別支援学校の定義や、他の支援制度との違い、現状についてわかりやすく整理していきます。
特別支援学校の定義
特別支援学校とは、心身に障害のある子どもが通うことを目的とした学校で、障害の状態や程度に応じた特別な教育を受けられる場所です。学習の過程は、一般の学校と同様に「幼稚部」「小学部」「中学部」「高等部」に分かれており、それぞれの発達段階に応じた支援が行われます。
もともとは「盲学校」「ろう学校」「養護学校」といった名称で分かれていましたが、2007年の法改正により、これらすべてが制度上「特別支援学校」として統一されました。現在でも学校名に旧名称が残っている場合がありますが、すべて特別支援学校に該当します。こうした制度の変更により、多様な障害に対応した教育の場が整備されています。
特別支援学校と特別支援学級・通級の違い
- 特別支援学校:障害のある子どもが通うために設けられた独立した学校で、個別性に応じた支援体制が整っています。
- 特別支援学級:通常の小学校や中学校の中に設けられた学級で、学習や生活に困難がある子どもが在籍します。学校生活の多くを支援学級で過ごすスタイルです。
- 通級:通常学級に在籍しながら、必要な時だけ別室などで個別の指導を受ける仕組みです。比較的軽度な支援ニーズに対応します。
それぞれの制度には特徴があり、進路を考える際は、学校との連携のもとで、どの形がもっともお子さまに合っているかを検討することが大切です。
特別支援学校の現状
文部科学省の調査によると、2021年度時点で全国には1,160校の特別支援学校が設置されています。こうした学校は、都道府県ごとに設置されており、地域によってその支援内容や専門性に特徴があります。
また、2023年度の報告によると、特別支援学校に在籍する児童・生徒数は151,358人と、過去最多を記録しました。発達障害をはじめ、さまざまな障害をもつ子どもたちが適切な教育環境を求めて、特別支援学校に通うケースが年々増加している現状が見てとれます。
これは、障害の理解や支援の必要性が広く社会に浸透してきた結果とも言え、保護者にとっても、より多くの選択肢が用意される時代になってきていると言えるでしょう。
特別支援学校の対象は?発達障害のある子どもは入学できる?
特別支援学校は、すべての子どもが自由に選べる学校ではありません。入学には一定の条件があり、対象となる障害の種類や程度が定められています。発達障害のあるお子さまが進路を考えるうえで、「うちの子は特別支援学校に入れるの?」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、どのような障害が対象となるのかをわかりやすく紹介したうえで、発達障害の場合の対応についても解説します。
①視覚障害
視覚障害は、視力や視野などの視覚機能に永続的な低下がある状態を指します。特別支援学校では、次のような状態の子どもが対象となります。
- 両目の視力がおおむね0.3未満
- メガネやコンタクトレンズを使用しても、通常の文字や図形の認識が困難
- 文字の読み書きや、人・物の確認に大きな支障がある
このような場合、視覚特別支援学校(旧・盲学校)などで、点字や拡大教材を用いた指導が行われます。
②聴覚障害
聴覚障害は、音や言葉の聞き取りに支障がある状態を指します。特別支援学校の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上
- 補聴器などを用いても、通常の話し声や環境音の聞き取りが困難
聴覚特別支援学校(旧・ろう学校)では、手話や指文字を用いた指導や、視覚的な学習支援が行われます。
③知的障害
知的障害は、知的な発達の遅れがあり、日常生活にさまざまな困難が生じる状態です。以下のような基準で特別支援学校の対象となります。
- 知的発達の遅滞があるうえで、意思疎通に困難があり、日常生活での多くの場面に援助が必要
- 上記に該当しなくても、社会生活への適応が著しく難しいと判断される場合
知的障害に対応した特別支援学校では、学習面だけでなく、生活スキルや社会参加に必要な力を育む指導が行われます。
④肢体不自由
肢体不自由とは、病気や事故などによって身体の運動機能に障害があり、日常動作が制限される状態を指します。特別支援学校では、次のような子どもが対象となります。
- 補装具を使用しても、歩行や筆記などの基本的動作が困難
- 上記に該当しない場合でも、常に医学的な観察や支援が必要
肢体不自由を対象とした学校では、バリアフリーな環境の中で、安全かつ丁寧な支援体制が整備されています。
⑤病弱
病弱の対象は、慢性的な疾患や身体虚弱により、日常的な医療支援や生活上の配慮が必要な子どもです。
- 呼吸器や腎臓、神経系の慢性疾患があり、継続的な管理が必要
- 身体が虚弱であり、生活上の制限や環境調整が常に求められる
こうした子どもには、医療的ケアと教育を両立できる支援体制が求められます。
発達障害の場合は入学できる?
実は、特別支援学校の入学条件として「発達障害」という記載は、制度上は明確に定められていません。しかし、発達障害のあるお子さまでも、就学相談を経て、特別支援学校に入学するケースは多数あります。
たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)やADHDなど、発達の特性によって学習や生活への著しい支援が必要と判断された場合には、知的障害の有無にかかわらず、特別支援学校への就学が検討されます。
最終的な判断は、教育委員会との「就学相談」によって行われるため、お子さまの状態や支援の必要性に応じて、個別に対応されます。「発達障害だから支援学校に行けない」と決めつけず、まずは就学相談でしっかりと状況を共有することが大切です。
就学相談について詳しく知りたい場合は、下記記事をご確認ください。
特別支援学校の教育環境・学べること
特別支援学校は、心身に障害のある子どもが安心して学び、社会の中で自立して生きていく力を育むことを目的とした教育機関です。ここでは、特別支援学校ならではの教育環境や、具体的にどのような内容を学べるのかを解説します。
特別支援学校の教育環境
特別支援学校の大きな特徴のひとつが、少人数で構成された学級編成です。生徒一人ひとりの障害の状態や特性に応じた、きめ細やかな指導やサポートを行うために、以下のような上限が定められています。
- 小学部および中学部:1学級あたりの上限は6人、平均は3人前後
- 高等部:1学級あたりの上限は8人
少人数制により、教師は個々の生徒の状態をしっかりと把握し、個別の支援計画に基づいた教育を実施することが可能です。また、教員の他に看護師や作業療法士、言語聴覚士などが在籍していることもあり、教育と療育が一体となった支援が受けられる点も大きな特徴です。
特別支援学校で学べること
特別支援学校では、文部科学省が定めた特別支援学校独自の学習指導要領に基づいて、障害のある子どもが自立に向けて力をつけられるような教育が行われています。とくに「自立活動」と呼ばれる支援が重視されており、次のような内容に取り組みます。
①基本的な生活習慣や社会性
日常生活に必要な「起床・睡眠」「着替え」「食事」「排泄」などの生活習慣を身につける支援が行われます。また、他者とのかかわりやマナーを学ぶことで、社会性の育成にもつなげます。
②健康の保持(生活リズムや生活習慣の形成、病気の状態の理解など)
生活リズムを整えることや、健康的な食生活、病気や自分の体調について理解することを学びます。医療的ケアが必要な子どもに対しては、学校と医療スタッフが連携して支援を行う場合もあります。
③障害による学習上の困難を克服するための支援
たとえば、発達障害により集中が難しい、指示を理解しにくいといった課題に対して、構造化された環境づくりや個別対応による支援を行い、学習に前向きに取り組めるようサポートします。
④障害特性に応じたICT機器や補助具の活用
視覚や聴覚、肢体などの障害に応じて、タブレット・拡大読書器・音声ソフト・スイッチ操作などのICT機器を活用した教育も行われています。これにより、コミュニケーションや表現の幅が広がるとともに、自立した学習が可能になります。
このように、特別支援学校では、「学力の定着」だけではなく、生活全体にわたる力を身につけることを大切にしています。お子さまの特性に合わせた教育が受けられることで、無理なく着実に成長していける環境が整えられています。
特別支援学校に通うまでの流れ
特別支援学校への入学を検討する場合、保護者が「いつ・何をすればいいのか」がわからず、不安を感じることも多いでしょう。実際の就学までには、就学相談や健康診断など、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、特別支援学校に通うまでの一般的な流れをご紹介します。なお、スケジュールや手続きの詳細は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。
【STEP1】入学1年前の4月頃まで:情報収集を行う
まずは、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室など、複数の就学先の選択肢について情報収集を行いましょう。各自治体や学校が実施している見学会や説明会に参加することで、実際の教育内容や支援体制を知ることができます。
また、療育センターや教育相談窓口などで相談することで、進路選びのヒントが得られる場合もあります。
【STEP2】4月~9月頃:就学相談を行う
4月以降になると、多くの自治体で就学相談の受付が始まります。就学相談では、保護者やお子さまが教育委員会の担当者と面談し、お子さまの発達の状況や支援の必要性を共有します。
場合によっては、発達検査や専門医による意見聴取、園からの意見書提出などが求められることもあります。これらの情報をもとに、最適な就学先(特別支援学校、支援学級、通級など)を一緒に検討していきます。
【STEP3】10月~12月頃:就学時健康診断を行う
多くの自治体では、秋ごろに就学時健康診断が実施されます。健康診断は通常の小学校と同様に、身体測定や視力・聴力検査、内科・歯科検診などを行い、就学に向けた健康状態の確認を行います。
医療的ケアが必要なお子さまの場合には、このタイミングで個別の配慮や支援の検討が進められることもあります。
【STEP4】1月末まで:通学通知書を受け取る
就学相談や健康診断の結果をもとに、教育委員会が就学先を決定し、1月末頃までに「就学通知書(通学通知)」が送付されます。通知書には、お子さまが入学する学校名などが記載されています。
進路に関して不安がある場合は、通知が届いた時点でもう一度教育委員会に相談することも可能です。
【STEP5】2月~3月頃:入学説明会に参加する
就学先が決定すると、入学前の準備として学校主催の説明会や面談が行われます。学校生活の流れ、持ち物や制服、送迎の方法などについて詳しく説明されるほか、教員との面談や施設見学が行われることもあります。
入学前に不安や疑問を解消できる貴重な機会なので、積極的に参加しましょう。
このように、特別支援学校への入学は、「就学相談」を中心とした一連の手続きを経て決まります。進学の1年前から準備が始まるため、早めに情報を集め、相談先と連携しながら進めることが大切です。
また、自治体ごとにスケジュールや手続きの流れは異なるため、必ずお住まいの地域の教育委員会や学校に確認しながら、適切な準備を進めましょう。
特別支援学校のメリット・デメリット
特別支援学校は、障害のある子どもが安心して学べる環境が整った学校ですが、進路を選ぶうえでは「良い面」だけでなく、「気をつけるべき点」についても理解しておくことが大切です。
ここでは、特別支援学校を選ぶメリットとデメリットの両方を解説します。
特別支援学校のメリット
特別支援学校には、通常の学級や支援学級にはない、独自の支援体制や環境が整っています。主なメリットは以下の通りです。
子どもの特性に合わせた個別指導が受けられる
一人ひとりの障害特性や発達段階に応じた「個別の指導計画」が作成され、それに沿って日々の学びが進められます。苦手なことには配慮があり、得意なことを伸ばす支援が受けられます。
安心して学べる少人数制のクラス
教員の目が行き届きやすく、集団生活に苦手さがあるお子さまでも安心して過ごすことができます。トラブルや不安が起きた際にも、すぐに個別対応してもらえる体制が整っています。
社会生活に必要なスキルが学べる
日常生活に必要な動作やルール、社会性を育むプログラムが組み込まれており、「生きる力」を育てる教育が行われます。将来の就労や自立に向けた基礎づくりにもつながります。
自己肯定感を育みやすい
一人ひとりの成長に合わせて目標が設定され、達成体験を積みやすいため、「できた!」「わかった!」という成功体験が増え、自己肯定感の向上にもつながります。
保護者への支援や情報提供が受けられる
面談や家庭連携の機会が多く、保護者に対する支援も充実しています。同じ立場の保護者との交流機会がある学校も多く、孤立を感じにくい環境です。
特別支援学校のデメリット
一方で、特別支援学校には以下のような課題や検討すべきポイントもあります。
通学が大変な場合がある
地域によっては、特別支援学校が遠方にしかない場合があります。スクールバスが用意されていることもありますが、通学に時間や負担がかかるケースもあるため、通学手段の確認は重要です。
通常学級との交流の機会が減る
通常学級や地域の子どもたちと接する機会が少なくなるため、「地域でともに育つ」という面で不安を感じる保護者もいます。学校によっては交流学習を行っているところもありますが、頻度や内容はさまざまです。
学習内容が限られる場合がある
教育課程は生徒の障害特性に応じて柔軟に組まれているため、標準的な教科書やカリキュラムとは異なる内容になることがあります。高校卒業資格の取得を目指す場合には、進学先の高等部のカリキュラムも確認が必要です。
社会に出た際の適応に関する不安
特別支援学校の中では過ごしやすくても、卒業後に就労や地域生活へ移行する際、環境のギャップに戸惑うことがあります。将来を見据えて、社会とのつながりや地域との関わりを持つ経験も大切にしておきたいポイントです。
※参考
うちの子、特別支援学校に通った方がいい?迷ったらAIAI VISITに相談してみませんか?
「うちの子は特別支援学校に通った方がいいのだろうか」「知的障害もあるけれど、支援級とどちらが合っているのか分からない」と、進路選びで悩む保護者の方は少なくありません。
特に、発達障害と知的障害が併存している場合、特別支援学校がより適しているケースもあります。しかし、障害の特性や支援の必要度はお子さま一人ひとり異なるため、誰かと一緒に丁寧に検討することが大切です。
そんな時に活用できるのが、AIAI VISITの「保育所等訪問支援」です。
AIAI VISITでは、発達支援の専門知識と経験を持つスタッフが、お子さま一人ひとりの状況に合わせた支援を行っています。たとえば、次のような流れで進路選びをサポートしています。
- 普段通っている幼稚園や保育園を訪問し、お子さまの様子を観察
- 教育や支援の専門的視点から、強みや課題、配慮が必要な点を整理
- 特別支援学校・支援学級・通級指導などの選択肢を比較しながら、お子さまに合った進路を一緒に検討
お子さまの教育環境を選ぶことは、保護者にとってとても大きな決断です。だからこそ第三者の視点を入れながら、後悔しないための環境選びが非常に重要です。まずはAIAI VISITにぜひご相談ください。
まとめ
特別支援学校は、発達障害を含むさまざまな障害のある子どもたちが、安心して学び、社会の中で自立していく力を育むことができる教育の場です。少人数制のきめ細かな指導や生活スキルの習得など、子ども一人ひとりに寄り添った支援が行われています。
一方で、通学の大変さや進路の選択肢の幅など、事前に理解しておきたい点もあるため、メリット・デメリットをしっかりと把握し、お子さまにとって最適な選択ができるようにする必要があります。
もし「うちの子に特別支援学校が合っているのか分からない」と迷っている場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談してみることも大切です。AIAI VISITでは、保護者の不安や疑問に寄り添いながら、お子さまの発達や特性に応じた進路選びをサポートしています。
将来の可能性を広げるために、まずはお子さまに合った学びの場を一緒に考えてみませんか?