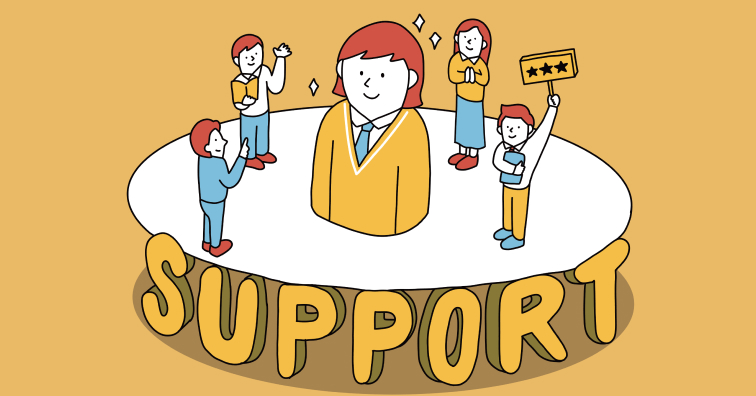就労移行支援とは?利用対象・利用する方法・メリットなどを徹底解説!
COLUMN

「障害のある子どもは、将来仕事に就けるのだろうか」「社会に出て、自分らしく働けるようになるにはどうしたらいいのか」そうした不安を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害のある方が一般企業への就職・復職を目指すために利用できる福祉サービス「就労移行支援」について、対象者の条件や支援内容、利用方法、費用、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
将来の選択肢を広げるための一つの手段として、就労移行支援の活用を検討する際の参考になれば幸いです。
就労移行支援とは
障害のある方が一般企業への就職・復職を目指す際に利用できる福祉サービスとして、「就労移行支援」があります。これは、障害者総合支援法に基づいて提供される就労支援サービスの一つで、働くことへの不安や課題を抱える方が、自分らしく社会に参加するためのステップとなる制度です。
就労移行支援では、ビジネスマナーやパソコンスキルなど、仕事に必要な知識・能力を身につけられるほか、履歴書の書き方や面接練習、就職活動のサポート、職場でのコミュニケーションの練習など、就労に向けた幅広い支援が受けられます。
ここでは、就労移行支援の目的や、他の就労系サービスとの違いについて詳しく解説します。
①就労移行支援の目的
就労移行支援は、障害のある方が社会で自立して働くための力を育てることを目的としています。そのための支援は多岐にわたり、次のような内容が含まれます。
- 職業能力の向上:作業訓練やビジネススキルの習得を通じて、仕事に必要な基礎力を身につけます。
- 就職活動の支援:履歴書の作成や面接対策、企業とのマッチングなど、就職に向けた具体的なサポートが受けられます。
- 職場定着の支援:就職後も継続して働けるよう、職場での課題や生活上の困りごとをサポートします。
- 自己肯定感の向上:小さな成功体験を積み重ねることで「自分にもできる」という気持ちを育み、前向きに社会参加できるよう支援します。
このように、単なる職業訓練にとどまらず、働くことを通じた自立と生活の安定を目指すのが、就労移行支援の大きな特徴です。
②就労移行支援と他の支援との違い
障害のある方が働くことをサポートする福祉サービスには、就労移行支援以外にもいくつか種類があります。それぞれの違いを理解することで、お子さまの状況に合った支援を検討しやすくなります。
| 支援の種類 | 対象者・特徴 | 報酬・給与の有無 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 企業への就職・復職を目指す人 | 雇用契約なし(原則無給) |
| 就労継続支援A型 | 一般就労が難しいが、雇用契約のもと働ける人 | 雇用契約あり・最低賃金以上の給与 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約が困難で、作業訓練を中心に支援が必要な人 | 工賃(作業報酬)あり |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人の職場・生活面のサポート | ー |
特に就労継続支援(A型・B型)は、就労移行支援とよく比較されますが、目的や利用対象に違いがあります。就労継続支援は「福祉的就労」として、一般就労が難しい場合の“働く場”を提供するのに対し、就労移行支援は“一般企業への就職”を目指す訓練の場といえるでしょう。
また、就労定着支援は、就職後の生活支援や職場の人間関係へのアドバイスなど、就労の継続を後押しする役割を担っています。
※参考
就労移行支援ではどんなことをする?
就労移行支援では、一般企業への就職を目指す障害のある方に対して、就労に必要なスキルや経験を身につけるための多面的なサポートが行われます。支援内容は事業所ごとに異なりますが、いずれも「働く力を育て、職場にスムーズに適応できるようにする」ことを目的としています。
ここでは、主に受けられるプログラムの内容と、それを支えるスタッフ体制について紹介します。
具体的なサービス内容
①職業訓練
働くうえで必要なスキルを、実践的な訓練を通じて習得します。
具体的には次のような内容があります。
- パソコン操作:Word・Excelなど
- ビジネスマナー:あいさつ、電話応対、敬語の使い方など
- コミュニケーションスキル:報連相の練習、相手の話の聞き方など
- チームワークを学ぶグループワーク
個人の特性に合わせた訓練が行われるため、無理なく少しずつ力をつけていけるのが特徴です。
②面接対策
就職活動の重要なステップである「面接」に備えて、繰り返し練習する機会が設けられます。
- 模擬面接で実践的な練習
- 自己PRや志望動機の整理
- 面接時の表情や話し方のフィードバック
こうした練習を通じて、自信を持って本番に臨めるようになります。
③職場実習
実際の企業などで短期間働く体験をすることで、実務感覚を養います。
- 業務の流れや職場の雰囲気を体感
- 「働く」ことへのイメージを具体化
- 実習先からフィードバックをもらうことで自分の課題を把握できる
実習を通じて、自分に合う職種や職場環境について理解が深まります。
④就職活動のサポート
個人の希望やスキルに合わせて、就職に向けた実践的なサポートが行われます。
- 求人情報の提供とマッチング支援
- 履歴書や職務経歴書の作成サポート
- 職場見学や面接の同行支援
一人で就職活動を進めるのが不安な方にとって、大きな安心材料となります。
⑤就職後のフォローアップ
就職して終わりではなく、働き続けること(職場定着)まで見据えた支援が続きます。
- 定期的な面談や相談対応
- 職場での人間関係や業務上の悩みへのアドバイス
- 必要に応じて企業側との調整やサポートも行う
この継続的な支援によって、就職後の不安や孤立感を軽減し、長く働くための基盤が整えられます。
どんなスタッフからサポートが受けられる?
就労移行支援では、さまざまな専門職がチームとなって支援を行っています。利用者一人ひとりの状況やニーズに合わせた柔軟な対応ができるよう、それぞれの専門性が活かされています。
| スタッフの種類 | 主な役割 |
|---|---|
| 就労支援員(ジョブコーチ) | 就職活動や職場実習の支援、職場との調整を行う |
| カウンセラー(心理師・精神保健福祉士など) | 不安やストレスへの心理的サポートを行う |
| 作業指導員 | 訓練内容の指導や作業のサポートを行う |
| 企業担当スタッフ | 実習・就職先企業との連携・調整を行う |
このように、多方面からのサポートを行いながら、利用者が「自分らしく働く」ことをしっかりと支えてくれます。
※参考
就労移行支援の対象者
「就労移行支援を利用してみたいけれど、うちの子は対象になるのだろうか?」そんな疑問を持つ保護者の方も少なくありません。
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための支援制度であり、対象者には一定の条件があります。
ここでは、就労移行支援の対象となる方の条件や、子どもが利用できるケースについて詳しく解説します。
就労移行支援を受けられる条件
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つです。
主に、次のような条件を満たす方が対象となります。
原則18歳〜65歳未満の方
就労移行支援を利用できるのは、基本的に18歳以上65歳未満の方です。
ただし、65歳の誕生日の前日までに障害福祉サービスの支給決定を受けていた場合は、65歳を超えても引き続き利用が認められることがあります。
障害や難病のある方
対象となる障害には、以下が含まれます。
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD など)
- 知的障害
- 精神障害
- 身体障害
- 難病(指定難病に該当するもの)
障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断書や意見書などで障害の状態が確認できれば、利用可能と判断されることがあります。
一般企業への就職を希望し、就労が見込まれる方
「働く意欲」があり、「支援を受けることで一般就労が可能と見込まれる」ことも条件の一つです。
具体的には、職業訓練や実習を通じてスキルを習得し、就職活動に臨む姿勢があることが重視されます。
就労移行支援は子どもも受けられる?
就労移行支援は、原則として18歳以上の方が対象です。
そのため、18歳未満の子どもが直接利用することは基本的にできません。
ただし、いくつかの例外的なケースがあります。
高校在学中に情報収集を始めることは可能
就労移行支援事業所の見学会や進路相談会などに参加し、将来の選択肢として情報を得ることは、高校在学中でも可能です。
保護者と一緒に見学することで、本人が将来の働き方をイメージしやすくなります。
特別な許可が出た場合、15歳以上で利用できるケースも
障害のある15歳以上の子どもについては、以下の条件を満たす場合に、特例として利用が認められる可能性があります。
- 児童相談所長が、就労移行支援の利用を適当と認める旨の意見書を市町村長宛に提出
- それに基づき、市町村がサービス支給決定を行った場合
このようなケースは少数ですが、進路に悩んでいる場合には、まずは市区町村や支援機関に相談することが大切です。
年齢に応じた他の支援を活用する選択も
18歳未満の子どもには、以下のような年齢に合った支援サービスの利用が推奨されます。
- 放課後等デイサービス
- 発達障害者支援センターの進路相談
- 学校の進路指導との連携
お子さまの状況や発達段階に応じて、どの支援が適しているかを柔軟に考えることが、将来の自立への第一歩につながります。
※参考
就労移行支援の利用可能期間
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すために、職業訓練や就職支援などを受けられる福祉サービスです。
この支援は、原則として最大2年間利用することができます。
2年間の間に、ビジネスマナーやパソコンスキルの習得、職場実習などを通して、就職に必要な準備を整えていきます。しかし、すべての方が一律に同じペースで進めるわけではありません。体調や障害特性などにより、2年間では就職に至らない場合もあります。
そのため、一定の条件を満たした場合には、利用期間の延長が認められることがあります。たとえば、
- スキルや知識がまだ十分に習得できていないと判断された場合
- 利用期間中に体調不良や症状の悪化などがあり、支援を継続的に受けられなかった場合
- その他、特別な事情があると認められた場合
こうしたケースでは、最長で1年間の延長利用が可能です。延長を希望する際は、就労移行支援事業所や市区町村の担当窓口に相談し、必要書類の提出や再審査が必要になる点にも注意が必要です。
お子さまの特性や状況に合わせて、無理のないペースで支援を受けられるよう、早めに相談を始めることが大切です。
※参考
就労移行支援の利用にかかる費用
就労移行支援は公的な福祉サービスですが、利用にあたって費用がかかる場合があります。具体的には、本人または配偶者の前年度の所得に応じて、サービス利用料の一部(原則1割)を自己負担する仕組みとなっています。
ただし、一定の所得以下であれば負担は軽減され、実質的に無料で利用できるケースも多くあります。たとえば、非課税世帯や障害年金のみを受給している方などは、自己負担が発生しないことが一般的です。
| 区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) | 9,300円/上限 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります
また、利用料以外にも、以下のような実費負担が生じる場合があります。
- 通所時の交通費(自宅から事業所までの往復交通費)
- 食事代(事業所で昼食が提供される場合)
- イベントや研修参加費用(企業見学や特別プログラムなど)
これらの費用は事業所や地域によって異なりますが、自治体や事業所によっては補助制度が用意されている場合もあります。交通費の一部支給や昼食の無料提供など、利用者の経済的負担を減らすための取り組みも見られます。
また、生活保護や障害年金を受給している場合には、それらの給付を活用して負担を軽減することが可能です。不明点がある場合は、まずは就労移行支援事業所やお住まいの自治体窓口に相談してみましょう。
お子さまの将来を見据えた進路選びにおいて、費用の不安がある場合も、支援制度をうまく活用することで安心して利用を検討できます。
就労移行支援を利用するまでの流れ
就労移行支援を利用したいと思っても、「どうやって申し込めばいいの?」「何を準備したらいいの?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、就労移行支援の利用を開始するまでの一般的な流れと、必要な手続きについて順を追ってご紹介します。
①自治体窓口や事業所に利用を相談する
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、気になる就労移行支援事業所に相談してみましょう。
事業所によっては、見学や説明会、体験利用などを受け付けているところもあります。
事前にお子さまの状況や希望を共有しておくと、より具体的なサポート内容を教えてもらえるため安心です。
②事業所の比較検討を行い、利用先を決める
就労移行支援事業所は民間や社会福祉法人などが運営しており、プログラムの内容や支援体制に違いがあります。
比較の際には以下のようなポイントを確認しましょう。
- プログラムの内容(職業訓練・実習・就活支援など)
- 就職実績や定着率
- スタッフ体制や支援の手厚さ
- 通いやすさ(立地・交通手段)
可能であれば複数の事業所を見学し、お子さまに合った場所を選ぶことをおすすめします。
③障害福祉サービス受給者証を申請する
就労移行支援を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
これは、福祉サービスの利用に必要な資格証明書で、市区町村への申請によって取得します。
申請には以下のような書類が必要です。
- 医師の診断書または意見書
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバー関連書類 など
詳しくは自治体窓口で確認し、必要書類を早めに準備しておきましょう。
④利用が決定したら、事業所と契約を結ぶ
受給者証の発行後、いよいよ就労移行支援の利用がスタートします。
利用を希望する事業所と正式に契約を結ぶことで、通所や訓練が始まります。
契約の際には、通所日数や訓練内容、費用の説明などがあるため、わからないことは事前に確認しておくと安心です。
このように、就労移行支援の利用にはいくつかの手続きが必要ですが、事業所や自治体がサポートしてくれる場合が多いため、不安なことは遠慮せず相談してみてください。
お子さまに合った支援を受けるためにも、早めの情報収集と準備をおすすめします。
※参考
就労移行支援を利用するメリット・デメリット
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための有効な支援制度です。
一方で、利用を検討する際には「本当にうちの子に合っているのか」「不安な点はないか」と、慎重になる保護者の方も多いでしょう。
ここでは、就労移行支援の主なメリットとデメリットを客観的に整理し、お子さまにとって適切な選択肢かどうかを検討する材料としてご紹介します。
就労移行支援を利用するメリット
就職活動のサポートが充実している
就労移行支援では、求人の紹介、履歴書の添削、模擬面接など、就職活動に必要な支援を総合的に受けることができます。
一人では難しい部分も、専門スタッフの伴走によって着実に進められる点は大きな魅力です。
自己肯定感の向上につながる
訓練や実習を通じて「できた」「認められた」という経験を積み重ねることで、自信や達成感が生まれ、自己肯定感が高まるという声も多く聞かれます。
精神面の成長をサポートするカリキュラムも多く、お子さまの社会性や自立への意欲向上にもつながります。
継続的なサポートが受けられる
就労移行支援の利用終了後も、「就労定着支援」という制度を通じて、職場で安定して働き続けるための継続的な支援が受けられます。
就職がゴールではなく、長く働き続けることを支える体制が整っているのは、大きな安心材料です。
就労移行支援を利用するデメリット
サービスの質に地域差がある
事業所によって提供されるプログラムの内容やスタッフの対応には差があります。
なかには「訓練が単調」「就職に結びつかない」と感じる場合もあり、事前の見学や比較検討が重要です。
利用開始までに時間がかかることがある
利用には、障害福祉サービス受給者証の申請や契約手続きが必要なため、すぐに通い始められるわけではありません。
タイミングによっては、申し込みから利用開始まで数週間以上かかる場合もあります。
モチベーションに左右されやすい
就労移行支援はあくまで“通所型”のサービスであり、利用者自身の意欲や継続力が重要になります。
通所に対する負担や「働くこと」に対する不安が強い場合、通い続けるのが難しくなることもあるため、お子さまの状態に合った支援内容かどうかの見極めが大切です。
就労移行支援には、就労に向けた手厚いサポートがある一方で、選ぶ事業所や本人の状況によっては効果が十分に発揮されにくいこともあります。
メリット・デメリットを丁寧に整理しながら、お子さまの将来を見据えて選択することが大切です。
まとめ
就労移行支援は、障害のある方が自分らしく社会に参加し、安定した就労生活を送るための支援制度です。
職業訓練や就職活動のサポート、就職後のフォローアップまでを一貫して行い、一般企業への就職という目標に向かって伴走してくれます。
制度の対象年齢や利用条件、サービスの内容にはさまざまな特徴があるため、「うちの子に合っているのか」「いつ頃から検討すればいいのか」といった不安を持つ保護者の方も多いでしょう。
しかし、お子さまの年齢や特性に合わせて支援を選び、必要な情報を早めに集めておくことで、より安心して進路を考えることができます。
費用面の負担や、事業所選びの難しさといった課題もありますが、それ以上に「働く力」や「自信」を育むことができるのが、就労移行支援の大きなメリットです。
お子さまが将来、自立して働くことを目指す上での選択肢の一つとして、就労移行支援の活用を前向きに検討してみてください。