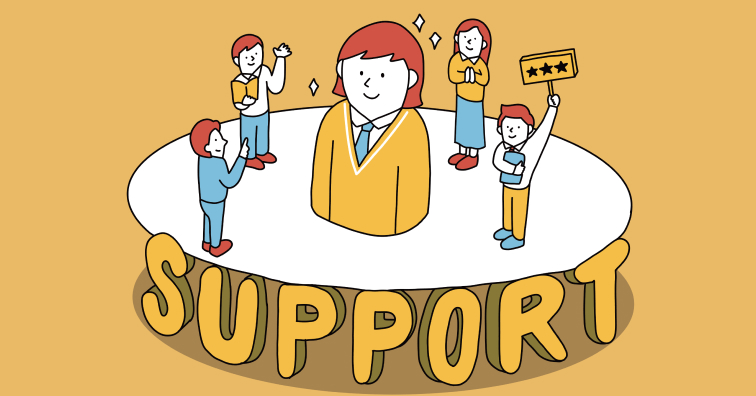強度行動障害の特性とは?原因や対応方法で大切にしたいポイントを解説します!
COLUMN

強度行動障害とは、自傷行為や他傷、食事関係や排泄関係の強い傷害など、生活に大きな支障をきたす行動が繰り返し見られる状態のことを指します。特に発達障害や知的障害など、子どもの特性と環境の不適合により見られることが多く、家庭や学校など日常生活の中での対応・支援が重要です。
今回は、強度行動障害の特性や原因、支援方法について詳しく解説するとともに、強度行動障害のある子どもとの接し方について紹介します。
強度行動障害とは?
強度行動障害とは、自分や他者の安全に大きな影響を及ぼす行動が頻繁に見られる状態を指します。具体的には、自分を傷つける「自傷」、他者に危害を加える「他害」、異常な睡眠リズムの乱れ、「異食」と呼ばれる食べ物ではないものを口にする行動、物を壊すなどの行為が挙げられます。これらの行動が繰り返されることで、日常生活や社会生活に支障をきたし、特別な支援や配慮が必要となるケースがあります。
なお、強度行動障害は医学的な診断名ではなく、行政や福祉の分野で支援の必要性を判断するために用いられる用語です。原因はさまざま考えられますが、発達障害などの特性と結びついて現れることがあると考えられています。
強度行動障害が見られる時は、適切な支援を通じて本人や家族・周囲の人々の生活の質を向上させることが重要です。
強度行動障害の具体的な行動とは
強度行動障害のある方の場合、日常生活に深刻な影響を及ぼす行動が見られることがあります。これらの行動は、頻度や強さによって「強度行動障害」と判断されることがあります。以下に、具体的な行動とその特徴について解説します。
① ひどい自傷
自分自身を傷つける行動が頻繁に見られる場合があります。
具体的には、自分で自分の頭を壁に打ち付ける、皮膚を引っ掻く、自分自身の爪を剥ぐなどの行為が挙げられます。
このような行動は、怪我や感染症のリスクを伴うため、早急な対応が必要です。
② 強い他傷
強度行動障害の場合、他者に対して暴力を振るう行動が繰り返されることがあります。
具体的には、噛みつく、蹴る、殴る、髪を引っ張る、頭突きをするなど、相手が怪我をしかねない行動が挙げられます。
これにより、周囲の安全が脅かされるだけでなく、人間関係の構築にも支障が生じる場合があります。
③ 激しいこだわり
特定の物事やルールに対する強い執着があり、それが崩れると激しいパニックや反応を引き起こすことがあります。
例えば、強く指示をしてもどうしても服を脱ぐ、どうしても外出を拒み通す、忘れ物をしたと感じたらどれだけ離れていても取りに戻るなどの行動を、止められても止められないことを指します。
このような強度行動障害の行動により、柔軟な対応が難しく、本人が強いストレスを感じるだけでなく、行動を共にする家族にとっても支障が生じる場合が多くなります。
④ 激しいもの壊し
家具や家電などを破壊する行動が見られる場合があります。
例えば、ガラス、家具、ドア、茶碗、椅子、眼鏡などを壊すことで、自分や周囲に怪我のリスクがあっても壊すことを止められないことを指します。
これにより、家庭や施設での生活環境が大きく損なわれることがあります。また、服をなんとしてでも破ってしまうことなども含まれます。
⑤ 睡眠の大きな乱れ
夜間に眠れない、昼夜逆転するなど、睡眠リズムが著しく乱れることがあります。本人が眠れないというだけではなく、ベッドについていられず人や物に危害を加える場合もあり、家族も疲弊することがあります。
⑥ 食事関係の強い障害
テーブルごとひっくり返したり、食器ごと投げたりと、椅子に座って他者と一緒に食事をすることが難しい状態を指します。
他にも、「異食」と呼ばれるような、食べ物ではない物(便や釘・石など)を口にする行動が見られることや、特定の食品に強くこだわるケース、食べ過ぎ・食べなさすぎが起こることもあります。
⑦ 排泄関係の強い障害
排泄のコントロールが難しい場合や、排泄物に対する異常な関心が見られることがあります。
具体的には、便を手でこねたり、便を投げたり、便を壁面になすりつけるなどの行動が見られることがあります。
これにより、生活の質が低下するだけでなく、衛生面での課題も生じます。
他にも、著しい多動や、通常と違う声を上げたり、大声を出したりするなどの行動が見られたり、パニックへの対応が困難なケースや、他者に恐怖感を与えるほどの粗暴な行為があり周囲が対応できないケースなども、「強度行動障害」と判断される場合があります。
これらの行動が日常的に見られ、頻度や強度が高い場合、専門家による適切な支援が必要です。家族だけで抱え込まず、行政や専門機関に相談してみましょう。
※参考記事※
強度行動障害の判定基準は?
強度行動障害は、医学的な診断名ではなく、行政や福祉の現場で必要な支援を判断するために用いられる用語です。そのため、支援の必要性を評価するための客観的な基準が設定されており、評価を通じて、本人に適した支援を提供し、家族や支援者の負担軽減を図ることが目指されています。
今回は評価基準として、厚生労働省が定めている「強度行動障害児(者)の医療度判定基準」と、「ABC-J(異常行動チェックリスト)」について解説します。
強度行動障害判定基準項目について
強度行動障害の判定は、行動の頻度や強度、支援の必要性を総合的に評価するスコアリングによって行われます。厚生労働省が定める判定基準には、以下のような項目が含まれます。
行動スコア
「自傷」「他傷」「物の破壊」「異食」「睡眠の乱れ」「排泄の問題」など、特定の行動に対する評価が行われます。それぞれの項目について頻度や強度を点数化し、合計スコアが一定以上である場合に「強度行動障害」と判定される可能性があります。
医療度判定スコア
医療的ケアの必要性を評価するスコアです。例えば、てんかん発作の頻度や医薬品の投与状況など、医療面での支援の必要性が点数化されます。このスコアは、福祉サービスの調整や支援計画の立案において重要な役割を果たします。
これらの判定基準に基づき、必要な支援の種類や程度が検討されます。判定結果は、福祉サービスの利用可否や支援プランの作成に直結するため、適切で詳細な評価が求められます。
ABC-J(チェックリスト)による評価について
強度行動障害の判定における行動評価ツールとして「ABC-J(異常行動チェックリスト:Aberrant Behavior Checklist Japan版)」が使用されることがあります。このチェックリストは、行動問題を定量的に評価するために作成されたもので、以下の5つのカテゴリーに分けられています。
- 易怒性:攻撃性や怒りを示す行動。
- 社会的退行:他者との関わりが乏しくなる行動。
- 不安/抑うつ:不安や気分の落ち込みに関連する行動。
- 過活動:極端な多動や集中力の欠如。
- 不適切な言語使用:社会的に不適切な発言や言葉の使い方。
判定する際は、保護者や支援者が日常的な行動を観察し、これらの項目について評価を行います。このチェックリストにより、どのような支援が必要かを具体的に把握することが可能になります。
ABC-Jを用いた評価は、行政や福祉機関における判断材料として活用されるだけでなく、支援計画の基礎資料としても役立ちます。このようなツールを活用することで、強度行動障害を持つ方への支援がより効果的に行えるようになります。
※参考記事※
強度行動障害の原因
強度行動障害の原因は、さまざまな要因が考えられますが、一部では発達障害によく見られる特性と周囲の環境との不適合が大きく関係していると考えられています。
重度の知的障害(知的発達症)や自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもにおいて、強度行動障害もあわせて見られるケースがあります。しかし、発達障害の診断有無にかかわらず、特性と環境の不適合により、強度行動障害が現れる可能性が高くなると考えられます。以下に、主な特性と強度行動障害との関連性について解説します。
① 社会性の特性
強度行動障害は、社会性に関する特性が原因となる場合があります。
例えば、自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもによく見られる、「他者の気持ちを推測することの困難さ」や、「社会的な状況を理解する力の不足」によって、周囲と円滑な関係を築くことが難しい場合があります。これが原因で、相手の意図を誤解して攻撃的な行動に出たり、周囲から期待されていることの理解が難しく、場にそぐわない行動をしてしまったりすることが考えられます。
② コミュニケーションの特性
コミュニケーションに困難さを抱える子どもは、自分の意思や感情をうまく伝えられないため、フラストレーションを感じやすくなります。その結果として、自傷や他傷など、強度行動障害につながる行動が見られる場合があります。
例えば、言葉での表現が難しい場合、泣き叫んだり物を壊したりすることで感情を表現しようとすることがあります。
③ こだわりの特性
強いこだわりやルールへの執着も、強度行動障害の原因になりうると考えられています。
例えば、予定の変更や予期しない出来事に直面した際、パニック状態になったり、極端な行動に出たりすることがあります。また、こだわりが強いことで、できることやすることが極端に少なく、暇をつぶすために自傷行動をしてしまうケースもあります。こだわりの特性が見られる場合、気持ちを切り替えることや、特定の行動を止めることが困難な場合も多く、強度行動障害につながる行動も止められないことがあります。
④ 感覚の特性
感覚過敏や鈍感といった感覚の特性も、強度行動障害の一因と考えられています。
例えば、音や光、匂いなど特定の刺激に対して極端に敏感な場合、それらの刺激がストレスとなり、そのストレスを軽減しようとして不適切な行動が見られる場合があります。逆に、感覚が鈍感な場合には、自傷行為などで感覚を刺激しようとするケースもあります。
他にも、衝動性を抑えることが苦手な場合は、突発的な飛び出しや奇声・大声をあげるなどの癇癪が見られる場合もあります。
このように強度行動障害は、子どもの特性と、周囲の環境が合わないことによって引き起こされることがあると考えられています。子どもの特性を理解し、適切な環境調整や支援を行うことで、強度行動障害につながる行動の改善や本人のストレス軽減が可能になります。困った行動が見られる場合、またそれにより日常生活に支障が生じている場合は、専門機関への相談や支援を活用することが重要です。
強度行動障害の特性がある子どもへの対応で大切にしたいこと
強度行動障害のある子どもとの関わり方には、日々の活動や環境を工夫することが重要です。子どもの特性に合った接し方を見つけ、本人が安心して生活できるよう、強度行動障害のある子どもへの接し方のポイントを以下に紹介します。
① 安定して行える日中活動を確保する
日中の活動を安定させることは、子どもの行動を落ち着かせるために重要です。活動の種類やスケジュールは、本人の特性や興味に合わせて設定するのが望ましいでしょう。
例えば、絵を描く、散歩をする、特定の作業を繰り返すなど、子どもが集中しやすい活動を取り入れると良いでしょう。また、活動の間に休憩時間を挟むことで、無理なく取り組める環境を整えることが大切です。
② 安心して過ごせる環境を整える
強いストレスやフラストレーションが、強度行動障害として現れている可能性が考えられるため、子どもが安心して過ごせる環境作りも大切です。
例えば、感覚の過敏さや刺激への反応を考慮し、騒音を減らす、照明を柔らかくするなど、環境を調整することも重要です。
また、子どもが好むアイテムや安心感を与える物を用意しておくと、不安感を軽減しやすくなります。安全なスペースを確保することで、子ども自身も安心して行動できることにつながります。
③ 一人で気持ちを落ち着けられる活動を見つける
子どもが一人で気持ちを落ち着けられる活動を見つけることは、行動の安定に繋がります。
例えば、好きな音楽を聴く、ブロックで遊ぶ、静かな場所で本を読むなど、リラックスできる時間を作りましょう。これらの活動を通じて、子どもは感情をコントロールする方法を学ぶことができるかもしれません。
単純に一人で過ごせる場所だけを用意しても、その場で何をしたら良いかわからないとストレスに感じたり、他者を巻き込もうとしたりして、問題が悪化する場合もあります。そのため、場所だけでなく一人で過ごすための活動もあわせて見つけることが重要と考えられています。
④ 見通しが立つスケジュールを実施する
日々のスケジュールが明確で予測可能であることは、強度行動障害のある子どもにとって非常に効果的と考えられています。
例えば、視覚支援ツールや絵カードを活用し、予定をわかりやすく提示することで、子どもは安心感を得られます。また、突然の変更がある場合は、事前に伝えたり、変更があることを示すカードを使用することで混乱を軽減することができるかもしれません。
⑤ 保護者・家族のレスパイトケアも重要
強度行動障害のある子どもを支える保護者や家族自身が健康でいることも重要です。レスパイトケア(短期休息サービス)を利用し、家庭外の支援を受けることで心身の負担を軽減しましょう。また、支援団体や専門家に相談することで、具体的な対応策や情報を得ることができます。家族全体が適切なサポートを受けることで、子どもとの関係もより良いものになるでしょう。
強度行動障害の特性がある子どもが受けられる支援は?
強度行動障害の特性がある子どもは、生活の中で困難を感じることが多く、場面にあわせた適切な支援が必要です。以下に、在宅での支援、施設での支援、そして相談先について解説します。
在宅で受けられる支援について
在宅で受けられる支援には、訪問型の支援や家庭環境を整えるためのアドバイスを提供するサービスがあります。
- 訪問支援サービス:専門のスタッフが家庭を訪問し、子どもや家族への支援を行います。具体的には、子どもとの接し方の指導や、日常生活の改善方法を提案します。
- 障害福祉サービス:居宅介護や行動援護といった支援が含まれ、食事や入浴の補助、外出時のサポートを受けることができます。
これらの支援は、家庭内で安心して生活を続けられるように設計されています。
施設で受けられる支援について
施設での支援は、より専門的で集中的なサポートを提供することが可能になります。
- 療育施設:発達障害や強度行動障害への対応に特化した施設で、子どもの特性に合わせた療育プログラムを実施します。行動面の改善や、社会性の向上を目的とした支援が行われます。
- 放課後等デイサービス:学校後の時間を利用して、子どもが楽しみながら学べるプログラムを提供します。遊びや学習を通じて、子どもの自立を促します。
- 短期入所施設:一時的に施設に預けることで、保護者の負担を軽減し、子どもが新しい環境で過ごす経験を積むことができます。自治体が提供する相談窓口や一時預かりサービスなどもあります。
これらのサービスを利用することは、子どもの発達を支えるだけでなく、保護者にとっての安心感にもつながります。
支援に関する相談先
支援に関する相談先として、以下のような機関が利用できます。
- 自治体の福祉窓口:障害福祉サービスの利用や、各種支援についての案内を行っています。
- 発達障害者支援センター:発達障害全般に関する相談が可能で、強度行動障害への対応方法についてもアドバイスを受けられます。
- 民間の支援サービス:専門的な支援機関は、療育や家族支援を行っています。また、オンライン相談も利用可能な場合があります。
これらの相談先を活用することで、子どもに合った支援を見つけ、家庭全体で適切なサポートを受けることができます。
AIAI VISITなら、強度行動障害の特性も含めて、お子さま一人ひとりに合わせたサポートを実施します
強度行動障害のある子どもたちへの支援では、家庭や学校など、日常生活の中で問題行動が見られた時にどのような支援を行うか、また問題行動が現れないようにどのように環境を整えるかが非常に重要です。
また、強度行動障害のある子どもと接する場合、周囲の大人が子どもの特性を理解し、子どもが安心して活動に取り組める環境を整えることが大切です。
しかし、専門的な知識や継続的なサポートがないと、日常生活の中で見られる困りごとが改善しなかったり、逆に悪化してしまったりすることも少なくありません。
AIAI VISITでは、お子さま一人ひとりの特性や個性に合わせたサポートを重視しています。子どもの安心感を大切にしながら、自信を持てるような成功体験を積み重ねるサポートを提供しています。例えば、お子さまの行動を丁寧に観察し、適切なタイミングで褒めることで、自己肯定感を育み、ポジティブな行動を引き出す工夫をしています。
さらに、強度行動障害に伴う感覚の特性や行動の課題に応じて、感覚統合を促す運動プログラムや、気持ちを落ち着ける方法を見つけるための活動も取り入れています。具体的には、リラックスできる静かな活動や、ストレスを軽減する粗大運動などを通じて、お子さまが楽しみながら自己調整能力を高める支援を行っています。
保護者の方も、強度行動障害につながるような問題行動に一人で悩むのではなく、外部のサポートを上手に活用し、一緒にお子さまの可能性を広げていきましょう。
まとめ
強度行動障害とは、日常生活に大きな支障をきたすような、激しい行動や不適切な行動が頻繁に発生する状態を指します。具体的には、自傷行為や他者への攻撃行為(他傷)、睡眠の乱れ、物を壊す行為、異食(食べ物以外のものを食べる)など、周囲の人々や子ども自身の安全を脅かす行動を指します。これらの行動が、単に一時的な問題ではなく、繰り返し発生し、通常の生活環境では適切に対応することが難しい場合に、「強度行動障害」と捉えられることがあります。
強度行動障害の特性がある子どもたちには、適切な支援が必要です。家庭や学校での対応とともに、専門的な支援機関や施設のサポートを活用することで、子どもの特性に合った方法で支援を行うことが可能になります。子どもが安心して過ごせる環境を整え、成功体験を積むことで自信を育むことができ、行動の改善にもつながります。また、保護者や家族のサポートも重要であり、無理をせず、適切なレスパイトケアや支援サービスを活用することが大切です。
強度行動障害を単に「困った行動」として捉えるのではなく、引き起こしている原因や適切な対処方法など、強度行動障害に対する正しい理解を深めることで、子どもに適した支援を提供し、生活の質を向上させることも可能かもしれません。
ぜひ一人で悩まずに、専門機関への相談を検討してみてください。