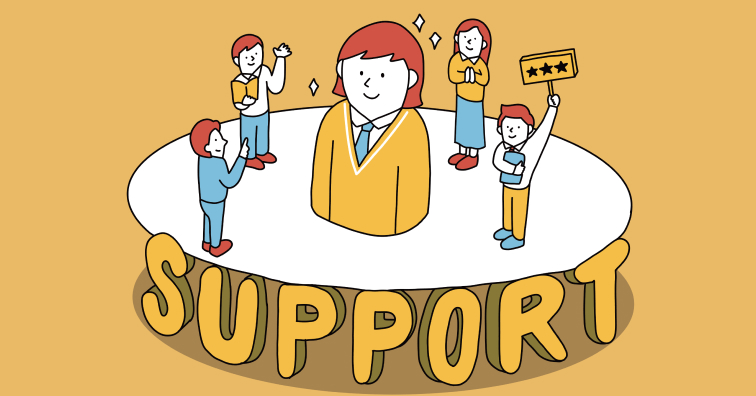【療育の専門家が解説】理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の違いは?お子さまの成長をサポートする専門家
COLUMN

発達に不安のあるお子さまをサポートする「療育」の現場では、「PT・OT・ST」という3つの専門職が活躍しています。これらはそれぞれ理学療法士(Physical Therapist)、作業療法士(Occupational Therapist)、言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)の略称であり、いずれも国家資格を持つリハビリテーションのプロフェッショナルです。
しかし、名前だけでは担当分野の違いが分かりにくく、「何をしてくれる専門家なの?」と疑問に思う保護者の方も多いでしょう。
本稿では、療育に関わるPT・OT・STの役割の違いとそれぞれの支援内容、さらに専門家同士の連携の重要性や家庭でのサポートのコツについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。お子さまに最適なサポートを選ぶためのヒントにしていただければ幸いです。
療育を支える三つの国家資格

療育の分野で活躍するPT・OT・STは、いずれも厚生労働大臣の免許を受けた国家資格保持者です。これらの資格は法律により位置づけが定められており、医療・福祉の現場で専門的なリハビリテーションサービスを提供する役割を担っています。
それぞれの専門家は担当領域こそ異なりますが、「お子さまの発達を促し、生活の質を向上させる」という共通の目的でチームの一員として働いています。
まずは、PT・OT・STそれぞれの定義や支援内容について詳しく見ていきましょう。
理学療法士(PT)とは
定義と法律上の位置づけ
理学療法士(PT)は、医師の指示のもとで「理学療法」を行うことを業とするリハビリの専門職です。法律上、身体に障害のある人に対し基本的動作能力の回復を図る理学療法を提供する国家資格者と定義されています。
「理学療法」とは、治療体操などの運動や温熱・電気刺激などの物理的手段を用いて身体機能の改善を図る施術のことです。PTは1965年に制度化された歴史ある専門職で、「身体を使ったリハビリの専門家」として、運動機能に困難を抱えるお子さまに専門的サービスを提供します。
運動発達・姿勢・バランスへの支援内容
PTの支援内容は、お子さまの運動発達や姿勢バランスの向上に特化しています。具体的には以下のような支援を行います。
- 「座る・立つ・起き上がる」といった基本的な動作の習得支援
- 「歩く・走る・ジャンプする」といった粗大運動の発達促進
- 姿勢の改善や体幹強化のためのトレーニング
PTは乳幼児期であれば寝返りやお座り、ハイハイなどの基本動作を練習し、幼児期~学童期では歩行や走る動作、ボール遊びなどダイナミックな運動遊びを取り入れながら体幹やバランス感覚を鍛えます。遊びの要素を交えて楽しく体を動かす中で、姿勢保持やバランス能力、筋力の発達を促進するのがPTの療育支援の特徴です。
作業療法士(OT)とは
定義と法律上の位置づけ
作業療法士(OT)は、理学療法士と同時期に制度化されたリハビリ専門職です。身体または精神に障害のある人に対し、応用的動作能力や社会適応能力の回復を図る作業療法を提供する国家資格者と定義されています。
法律上は医師の指示のもとで「作業療法」を業とする点でPTと類似しますが、担当する領域は日常生活活動(ADL)や遊び・学習動作といった「生活行為全般」にわたる点が特徴です。OTは「手先を使った活動や日常生活での作業」をリハビリ手段とする専門家であり、お子さまの生活動作の自立や発達を支援します。
日常生活動作(ADL)・遊び・学習の支援内容
OTの支援内容は、お子さまの日常生活における動作全般の発達支援です。具体的には以下のような支援を行います。
- 食事や歯みがき、着替え、排せつなどのADL(日常生活動作)の習得支援
- スプーンや箸の使い方、ボタンやファスナーの留め外しなど細かな手先の動作の指導
- お絵かきや工作、ブロック遊びなど遊びを通じた手先の巧緻性や認知能力の向上
- 感覚統合療法を取り入れた、感覚遊びによる落ち着きや集中力向上の支援
- 学齢期の書字動作練習や学習に必要な作業スキルの支援
OTは「生活で必要な動作を遊びに取り入れて練習し、できることを増やす」ことで、お子さまの生活の質(QOL)の向上を図っています。
言語聴覚士(ST)とは
定義と法律上の位置づけ
言語聴覚士(ST)は、音声機能・言語機能・聴覚に障害のある方に対して、その機能の維持向上を図るために言語訓練などを行う国家資格者です。言語聴覚士法により位置づけられ、医師または歯科医師の指示のもとで嚥下訓練や人工内耳の調整などの診療補助も行います。
簡単に言えば「ことばと聞こえ、食べることの専門家」であり、ことばによるコミュニケーションや飲み込みに課題のある人を支援するのがSTの役割です。法律上、失語症や構音障害に対する言語訓練など一部の業務は医師の指示無しでも独立して行うことが可能とされています。
言語・発音・嚥下・コミュニケーションの支援内容
STの支援内容は、お子さまの「話す・聞く・食べる」をサポートすることが中心です。具体的には以下のような支援を行います。
- 言葉の理解と言語表現の発達支援
- 発音(構音)の矯正
- 聞こえのトレーニングや補聴器の調整支援
- 摂食・嚥下(飲み込み)の機能支援
- コミュニケーション方法の獲得支援(絵カードやジェスチャーの活用など)
STの目標は、お子さまが自分の気持ちや意思を伝えられるコミュニケーション方法を身につけ、安心して食事ができるようにすることです。単なる発音練習に留まらず、お子さまのコミュニケーション全般を支える役割を担っています。
三職種の役割比較と連携モデル
支援領域・アプローチ・目標設定の違い
PT・OT・STの支援領域は以下のように整理できます
理学療法士(PT)
- 支援領域:身体の基本的な運動機能
- 主な対象:立つ・歩くなどの粗大運動や姿勢バランス
- 主なアプローチ:運動療法(エクササイズ)中心
- 最終目標:移動能力の確立や体力向上を通じた生活の自立度向上
作業療法士(OT)
- 支援領域:日常生活での応用的動作
- 主な対象:着替えや食事動作、遊びや学習など日常場面で必要な動作全般
- 主なアプローチ:遊びや作業活動を通じた訓練
- 最終目標:生活動作の自立および社会適応力の向上
言語聴覚士(ST)
- 支援領域:コミュニケーションと言語・嚥下機能
- 主な対象:言葉の理解・表出や発音、聞こえ、食べる機能
- 主なアプローチ:言語訓練や口腔機能訓練
- 最終目標:意思疎通能力の獲得と安全な摂食の実現
チーム連携が成果を高める具体例
多職種連携により相乗効果が生まれる具体例として、例えば脳性まひのお子さまの支援では、PTが立位や歩行訓練で身体機能を高めつつ、OTが座位での食事動作や玩具操作の練習を行い、STが発声や嚥下の訓練を担当します。
それぞれが専門領域からアプローチしつつも、「食事場面で安定して座れるようになれば発声訓練にも集中できる」など支援内容は相互に関連しています。週ごとのチームカンファレンスで情報共有し、目標をすり合わせながら進めることで、単一職種では得られにくい総合的な発達促進効果が期待できます。
お子さまの課題別・専門家選択ガイド
お子さまの発達上の課題に応じて、どの専門家の支援を優先的に受けるべきか判断する際の目安を示します。
ケース別推奨例
運動発達の遅れがある場合
寝返りができない、歩行開始が遅れている、姿勢がふらつくなどの場合は、理学療法士(PT)が第一の相談先です。基本動作や筋力バランスの専門家として、適切な運動訓練により発達を促してくれます。
日常生活動作が不器用な場合
食事や更衣がうまくできない、手先の操作が苦手などの場合は、作業療法士(OT)が適任です。生活動作の分析に長け、その子に合った練習方法を提案してくれます。例えば箸のトレーニングやボタンの練習など、遊び感覚で教えてもらえます。
言葉の発達に遅れがある場合
2語文が出ない、舌足らずな発音をするなどの場合は、言語聴覚士(ST)に相談しましょう。言葉の発達段階を評価し、適切な言語訓練プログラムを提供してくれます。構音障害についても専門的に診断し訓練します。
併存課題がある場合の連携パターン
実際には、お子さまの状況により複数の専門家の力を借りるケースも多くあります。例えば知的障害や発達障害では、運動面・認知面・言語面の課題が重複しがちです。このような場合、同時並行で複数のリハビリ専門職に通うことも選択肢となります。
信頼できる施設・専門家を選ぶ五つのチェックポイント
信頼できる施設・専門家を選ぶ五つのチェックポイント
1.資格保持と臨床経験年数
担当者が国家資格を有しているか、また小児分野での臨床経験がどれくらいあるかを確認しましょう。一般に経験年数が長いほど様々なケースを見てきていますが、新人でも熱意と最新知識でカバーしている場合もあります。目安として5年以上の小児リハ経験や療育分野での経験があれば安心材料と言えるでしょう。
2.評価・目標設定プロセスの透明性
優良な療育施設・専門家ほど、最初に丁寧な評価を行い、保護者に分かりやすくフィードバックしてくれます。個別支援計画書に評価結果・課題・短期目標・長期目標が具体的に明記されているか確認しましょう。
3.保護者との面談・フィードバック体制
保護者とのコミュニケーションが密に取れるかも重要なポイントです。定期的に面談や報告の場を設けているか、保護者の疑問や不安にきちんと答えてくれる体制かどうかを確認しましょう。
4.多職種連携の実績
お子さまの課題が多岐にわたる場合、一つの施設内でPT・OT・STが連携しているかどうかも大切です。見学や問い合わせ時に「他の専門職との連携はどのように行っていますか?」と質問してみましょう。
5.家庭支援プログラムの有無
施設での療育だけでなく、家庭での取り組み方も指導してくれるかをチェックしましょう。お子さまの成長には日常生活での積み重ねが大きく影響するため、家庭療育のサポートがあると望ましいです。
家庭でできる支援と施設連携のコツ
PT視点:粗大運動・体幹遊びの取り入れ方
家庭でできるだけ体を動かす遊びの機会を作ることが勧められます。例えば
- バランスボールやクッションの上で跳ねたり座ったりする遊び
- ボール遊びや公園の遊具を活用した全身運動
- 床にクッションやマットを敷いて不安定な足場を作る練習
- ハイハイ競争やトンネルくぐり遊びなどの全身運動
基本は「楽しく遊んでいたらいつの間にか運動能力が伸びていた」という形が理想です。
OT視点:生活動作を遊び化する環境設定
日常生活の動作そのものを遊びに変えてしまう工夫がおすすめです
- 「ぬいぐるみにご飯を食べさせる」などのおままごとで食事練習
- 雑巾がけ競争で床掃除と体幹トレーニングを同時に行う
- 「靴下ペア探し競争」や「タオルたたみリレー」で手先の練習
- お手伝いを遊び感覚で取り入れる
大人が手本を見せ、子どもが真似る形にすると分かりやすいです。上手くできたら思いきり褒め、一緒に達成感を味わいましょう。
ST視点:語りかけ・コミュニケーション環境づくり
日常的な語りかけの質と量を意識することがポイントです
- お子さまと遊ぶときや食事をするとき、「実況中継」のように話しかける
- 返事が返ってこなくても問いかけ、お子さまの発した言葉を繰り返して反応する
- ことばに親しめるオモチャ(動物の鳴き声が出る絵本など)を身近に置く
- 読み聞かせの時間を習慣化する
- ジェスチャーや指差しでも意思表示できたら受け止める
コミュニケーションは双方向のキャッチボールなので、親御さんも笑顔でレスポンスすることが、お子さまの言語意欲を引き出す近道です。
保護者からのよくある質問
Q: 複数の専門家に同時に通うべきでしょうか?
A: お子さまのニーズによります。課題の領域が明確に分かれている場合、必要に応じて複数のリハビリを併用することは効果的です。ただし、通わせすぎてお子さまの負担にならないよう配慮も必要です。一箇所の療育センターで多職種連携が整っているならそこで包括的に受けるのも良い選択肢です。
Q: 訓練の効果はどれくらいで実感できますか?
A: 個人差が非常に大きく、一概には言えません。数週間~数ヶ月で目に見える進歩を示すお子さまもいれば、もっと長い時間を要する場合もあります。焦らず取り組みを続けることが大切で、半年、1年というスパンで振り返ると成長に気づくことも多いです。短期的に結果が出なくても落胆せず、長期的視野でお子さまのペースを尊重しましょう。
Q: 家庭での訓練がうまく続かないときはどうすればよいですか?
A: まず大前提として、一人で抱え込まないことが大事です。うまくいかないときは一歩引いて深呼吸し、療育の専門家に率直に相談しましょう。頑張りすぎず小さな成功を褒める視点も持ってください。5分取り組めたら上出来、どうしても難しい日は思い切って休むなど、長期で一緒に取り組んでいくために無理のない家庭内での訓練目標を決めるのがおすすめです。
家庭療育は保護者の心に余裕がないと続かないと言われます。完璧を目指さず、周囲の支援者にも頼りながら、ゆるやかに継続していきましょう。
まとめ
PT・OT・STという三職種は、それぞれ専門分野とアプローチの違いはあるものの、チームで協働することでお子さまの発達を多方面から支えています。理学療法士は身体づくり、作業療法士は生活動作、言語聴覚士はコミュニケーションというように役割分担しつつも、連携することで「心・技・体」バランスよくお子さまを伸ばすことが可能です。
保護者の方々にはぜひ信頼できる専門家チームをパートナーに迎え、家庭と施設が一丸となってお子さまの成長をサポートしていただきたいと思います。悩んだときには一人で抱え込まず、遠慮なく周囲のリソースを活用しましょう。PT・OT・STそれぞれの知見を取り入れながら、お子さまの「できた!」という笑顔を積み重ねていく——それが療育成功の鍵です。
AIAI VISITでは一人ひとりの特性にフォーカスした丁寧なサポートを大切にしております。お気軽にご相談ください。