個別支援計画とは?発達障害のある子どもへの支援内容・記入例・保護者の関わり方まで解説
COLUMN
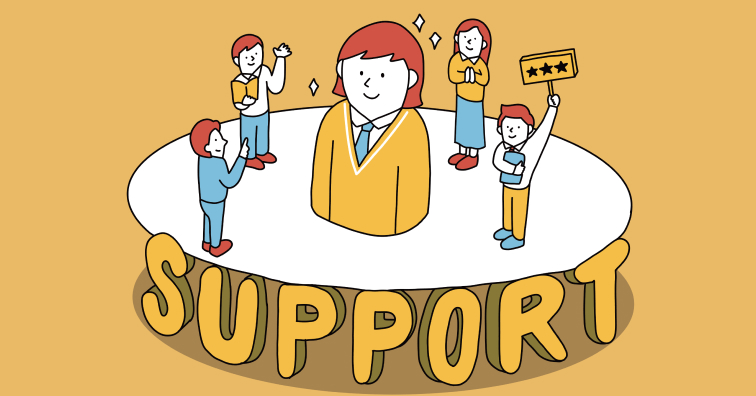
個別支援計画とは、障害のある方一人ひとりのニーズや特性に応じて支援の計画を記したものです。この記事では、発達障害などの障害のある子どもの支援のために作成する個別支援計画について、記載内容や作成手順、保護者の関わり方、作成のポイントなどの視点からわかりやすく解説します。
個別支援計画とは?
「個別支援計画」とは何か、どのような目的で作成されるものなのかを解説します。
①個別支援計画の定義と目的
個別支援計画とは、障害のある方一人ひとりのニーズや特性に応じて、支援の計画を記したものです。障害のある子どもを対象にした個別支援計画の場合、子ども本人や家族の意思・希望が日常生活に反映されるよう、必要な支援を検討して作成されます。
主に「何のための支援か(目標)」「どのように支援するか(方法)」「いつ見直すか(モニタリング)」などが記載されます。子ども一人ひとりの「自分らしい暮らし」や「成長」を実現するために、個別支援計画は非常に重要です。
②個別支援計画の作成主体と関係者
個別支援計画は、「サービス管理責任者(通称、サビ管)」という障害福祉サービスの専門職が中心となって作成します。ただし、家族、福祉サービスを行う支援員、学校関係者、医療関係者など、子どもに関わるさまざまな大人が個別支援計画の内容を共有し、チームで支援に取り組むことが大切です。
個別支援計画の作成には本人のほか保護者の意見も大切にされ、家庭での様子や子どもの将来に関する希望も反映されます。
個別支援計画に記載するべき内容
個別支援計画に実際にどのような項目が記載されるのかを解説します。
①アセスメント情報(本人の課題・特性など)
子どもの発達状況や障害の特性、生活上の困りごとなどを記載します。保護者からの聞き取りのほか、医師による所見や支援者による観察結果、発達検査の結果などを参考に、「何ができていて、何が苦手か」「どんな支援が必要・適切か」を整理します。
②本人や家族の希望
支援の方針を立てるには、本人や家族の意向や希望を詳しく知る必要があります。「どんな生活を送りたいか」「何をできるようになりたいか」「将来どんなふうになっていきたいか」など、本人や家族から聞き取って記載します。
③支援の具体的な方法
事業所や学校、家庭などにおいて、支援員や周りの大人が本人に対してどのようなことを意識して関わるか、どのような支援を行うかを具体的に明記します。例えば「着替えの見守り」「登園準備の声かけ」といった内容や、その際の言葉かけや提示の方法なども具体的に記載することがあります。
④短期・中長期の目標設定
数ヶ月〜1年以内に達成したい「短期目標」、将来的な自立を見据えた「中長期目標」をそれぞれ記載します。例えば、短期目標「5分以上座って話を聞ける」、中長期目標「放課後児童クラブに慣れて毎日通うことができる」といった内容を記載します。
⑤モニタリング・評価の方法
支援計画を立てて実施するだけではなく、支援の進捗や支援方法が子どもに合っているかどうかを確認するためのモニタリングや評価をおこない、必要に応じて支援を見直す必要があります。どのような方法・頻度でモニタリングするのか、その結果をもとに支援を見直す時期はいつにするのかも個別支援計画のなかに記載することがあります。
個別支援計画が必要な理由
個別支援計画はなぜ必要なのでしょうか。5つの理由にわけて説明します。
①子ども一人ひとりに合った支援を実現するため
一人ひとり、発達状況や特性・課題は異なります。効果的な支援をおこなうためには、画一的な支援ではなく個に応じた支援計画を立てることが大切です。個別支援計画作成にあたって本人に合った支援内容やアプローチを整理し、明記することで、子ども一人ひとりに合った支援を実現しやすくなります。
②保護者・支援者間での情報共有をスムーズにするため
多くの場合、障害のある子どもの支援には複数の大人が関わります。個別支援計画があることで、学校、福祉施設など、異なる場で関わる大人たちのあいだで支援の方針や子どもの情報を共有できます。個別支援計画には保護者の意向や希望も反映されるため、家庭と連携して一貫した支援を実現しやすくなります。
③支援の目標や進捗が明確になるため
「なにを目指して支援しているのか」「どのような段階を踏んで支援するのか」が具体的になることで、保護者も支援の意図を理解しやすくなります。個別支援計画をもとに進捗の評価やモニタリング、計画の見直しをおこなうことで、できるようになったことが明確に見えるという良さもあります。
④計画的な支援で子どもの成長を後押しできるため
「今何ができるようになりたいか」という短期的な視点だけではなく、「5年後、10年後、どのような姿を目指すか」という長期的な視点で、将来を見据えた支援の方向性を整理する役割もあります。
計画に沿って段階的に支援を進めることで、生活の自立や社会参加など、長期的なゴールを目指して子どもの成長を後押しすることができます。
⑤障害福祉サービスを適切に利用するために必要なため
放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを利用するためには、個別支援計画の作成が必要なケースがあります。サービス提供事業所もこの計画に基づいて支援を提供するため、正確かつ適切な内容であることが大切です。
個別支援計画を作成する上でのポイント
効果的な個別支援計画を作成するためのポイントと、そのために保護者が支援員に伝えると良いことを解説します。
①本人・家族の「願い」や「目標」を丁寧にヒアリングすること
計画の出発点は、本人や家族が「どのように生活したいか」「何をできるようになりたいか」「どうなっていきたいか」という希望や願いです。支援者の判断だけで個別支援計画を作成せず、本人・保護者からのヒアリングや話し合いを大切にしながら作成することが大切です。
個別支援計画の作成にあたって、面談の場では家庭での様子や困っていること、将来の希望なども遠慮せずに伝えるようにしましょう。
②本人の強みやできていることにも注目すること
苦手なことや課題だけでなく、「すでにできていること」「得意なこと」も把握することで、支援の方針を立てやすくなります。できていることを土台に新しい目標を立てたり、得意なことを生かした方法で支援するのが理想的です。
③具体的かつ実行可能な目標を設定すること
曖昧な目標ではなく、「◯ヶ月以内に△△ができるようになる」など、行動・期間・到達度が明確な目標を設定することが大切です。
目標が高すぎると支援を継続することが難しくなりますが、目標が低すぎても成長につながりません。本人にとってちょうど良い目標になっているか、定期的なモニタリングをして確認のうえ、必要に応じて目標の見直しをすることも大切です。
④支援内容や担当者を明確にすること
誰がどのような方法で支援するのかが曖昧なままだと、実際の現場で支援がズレてしまうリスクがあります。簡潔でも良いので、支援内容が具体的に記載されているか確認してみましょう。
⑤見直し(モニタリング)の仕組みを必ず設定すること
支援は一度立てて終わりではなく、定期的な振り返り・評価・見直しを行うことで、常に最適な内容に更新していくものです。支援者とのあいだに定期的な面談の場を設け、「支援方法や目標は子どもに合っているか?」「前回の面談のあとから新しく発生した困りごとはないか?」などを伝えるようにしましょう。
※参考
- (別紙1) 個別支援計画の記載のポイント(子ども家庭庁)
個別支援計画の作成の流れ
個別支援計画は誰がどんな手順で作成されるのかを具体的に解説します。
①アセスメント(課題分析)
最初のステップは、子どもの発達状況・生活環境・困りごとなどを把握する「アセスメント」です。保護者からのヒアリング、本人の様子の観察、医師の所見、他の支援者からの意見、発達検査の結果などを総合して整理します。保護者は子どもの「普段の様子」「困っていること」「得意なこと」などをできるだけ具体的に伝えるとスムーズです。
②原案作成とチーム会議
サービス管理責任者(サビ管)が、アセスメント情報をもとに計画の原案を作成します。その後、本人や保護者、放課後等デイサービスといった福祉サービスの支援員や学校の先生、医療関係者といった子どもに関わる大人を交えて「サービス担当者会議(ケース会議)」が開催されることが多いです。
この場で原案の内容を確認しながら、必要な修正や意見のすり合わせを行います。保護者の声が計画に反映されているか確認できる場でもあるので、疑問や要望があれば伝えるようにしましょう。
③計画書の完成と説明
ケース会議を踏まえて完成した計画書が関係者に共有されます。支援者から保護者への説明も行われ、内容に納得したうえで同意(サイン)を求められるケースもあります。わかりづらい表現や不安な点があれば、遠慮なく質問してください。
④モニタリング・見直しの実施
個別支援計画を作成したあとは定期的に「モニタリング(支援の振り返り)」を行い、目標の達成状況や支援の内容を確認します。年に1〜2回の頻度で再評価・見直しが行われ、必要に応じて計画の修正を行うのが一般的です。
モニタリング・見直しは、子どもの変化に気が付き、できるようになったことや新たな困りごとを確認できる機会でもあります。保護者として気づいた点や新たな困りごとや目標などがあれば伝えると良いでしょう。
個別支援計画の項目別書き方のポイント
特別支援学校への入学を検討する場合、保護者が「いつ・何をすればいいのか」がわからず、不安を感じることも多いでしょう。実際の就学までには、就学相談や健康診断など、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、特別支援学校に通うまでの一般的な流れをご紹介します。なお、スケジュールや手続きの詳細は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。
【STEP1】入学1年前の4月頃まで:情報収集を行う
個別支援計画の記載項目ごとの書き方のポイントと、質の高い計画を作成するために保護者にできることを解説します。
①アセスメント(本人の状況や課題)
発達や行動の特性、生活の中で困っていること、できていること、支援が必要な場面などを記載します。書き方のポイントは、できるだけ客観的に、日常での具体例を挙げることです。例えば「朝の準備で着替えに時間がかかる」「ざわざわしている教室にいるとパニックになる」などです。
保護者は、日常生活のなかで子どもが困っていることやスムーズにできていることをメモしておき、具体的に伝えられると良いでしょう。
②本人や家族の希望
何ができるようになりたいか、将来どうなりたいかなど、本人や家族が希望することを記載します。書き方のポイントは、「◯◯できるようになりたい」「△△にチャレンジしたい」「将来、○○な暮らしができている」など、できるだけ前向きな表現で書くことです。
保護者は、自分の子どもにどうなっていってほしいか、将来に向けてどのような姿を思い描いているかを率直に言語化してみてください。
③支援の具体的な内容
どんな支援を、どのように提供するかを記載します。例えば、「食事のときに○○と声かけをする」「登園準備の手順を視覚的に提示する」などです。書き方のポイントは、「見守り」「促し」「一緒に行う」など、実際の支援行動を明確に記載することです。
保護者は、家でやってうまくいった声かけや関わりを共有することで、支援内容に反映されやすくなります。
④短期・長期の目標設定
1〜3ヶ月で達成したい短期目標、半年〜1年先を見据えた中長期目標を記載します。書き方のポイントは、「どんな行動ができるようになるか」「どの程度までできるようになるか」を明確に設定することです。
保護者は、「どのようなことができるようになると日常生活がすごしやすくなるか」「最近の成長から感じたこと」などを伝えると良いでしょう。
⑤モニタリング・評価方法
支援が予定どおり行われているか、目標の達成度をどう確認するか、計画の見直し時期などを記載します。書き方のポイントは、評価の視点や記録方法、振り返りの頻度などを明記することです。
保護者は、子どもの変化で気が付いたことや気になることをメモしておき、支援がうまくいっているかを確認する機会としてモニタリングの場に参加すると良いでしょう。
なお、支援内容をよりわかりやすく整理するために、「5領域」に沿って記載されることもあります。「5領域」について詳しくは、関連記事をチェックしてください。
個別支援計画が正しく記載されなかった場合のリスク
個別支援計画を正しく作成することは、子どもに合った支援や支援者間での連携などにつながります。逆に、正しく内容が記載されなかった場合にはどのようなリスクがあるのか、解説します。
①子どもに合わない支援が行われてしまう
支援や個別支援計画に記載された内容に沿って行われるため、誤ったアセスメントや目標が計画に反映されると、子どもに合わない支援が続くことになります。結果として子どもの成長や自立を妨げたり、逆にストレスを増やす要因になる可能性があります。
②支援者間での情報共有がうまくいかなくなる
個別支援計画は、複数の支援者間で共通の支援方針を確認する役割を持っています。支援方法や目標の記載が曖昧だったり、保護者の希望が反映されていなかったりすると、支援の方向性にズレが生じるリスクがあります。
③評価や見直しが形骸化してしまう
個別支援計画にきちんとした目標や支援内容が記載されていないと、モニタリングや評価の場において振り返りが形式的になりがちです。「立てた目標のうちどこまで達成できたか」「今の支援方法が適切かどうか」を具体的に判断できず、支援の質が下がってしまいます。
④福祉サービスの利用に影響が出る可能性もある
個別支援計画は、放課後等デイサービスや短期入所施設など障害福祉サービスの提供に関係します。記載ミスや不備があると事業所側の運営や記録にも支障が出る可能性があります。場合によっては、サービスの継続利用や更新手続きに影響するかもしれないので、注意が必要です。
個別支援計画を作成する上での保護者の関わり方のポイント
個別支援計画を作成するのはサービス管理責任者ですが、その内容を検討するうえで、保護者の意見は非常に大切です。個別支援計画の作成に保護者はどのように関われば良いのか、解説します。
①家庭での様子や困りごとをできるだけ具体的に伝える
支援員や教員は子どもの施設や学校での様子はわかっても、家庭での様子までは見えません。なかには、家の外と中では見える面がちがう子どもたちもいます。家庭における子どもの様子や困りごとは、保護者がなるべく具体的に伝えましょう。例えば「朝の準備に30分以上かかる」「着替えは声かけがないと難しい」など日常の具体例を挙げることで、より的確なアセスメントが可能になります。
課題や苦手なことだけではなく、できるようになったことや工夫してうまくいっていること、得意なこともぜひ伝えてみてください。
②子どもの「得意なこと」「好きなこと」も共有する
個別支援計画を作成するにあたって、「できないこと」「苦手なこと」に注目しがちですが、子どもの得意なことや興味は支援方針を考えるうえで大切な手がかりになります。
「工作が好き」「電車に詳しい」「小さな子には優しい」などの情報は支援の工夫にも活かせるため、積極的に伝えてみてください。
③将来的な希望や生活像を話しておく
短期的な支援目標だけでなく、「将来的にはどんな生活をしてほしいか」も話しておくと、長期的な視点で支援をしやすくなります。
例えば「学校における集団生活にも慣れていってほしい」「将来は軽作業ができるようになってほしい」など、子どもの将来を見据えた希望があれば伝えると良いでしょう。
④気になることがあれば遠慮なく質問・相談する
ケース会議や説明の場で、「これはどういう意味?」「この支援は本当に必要?」と疑問に思ったら、率直に確認をしてみてください。個別支援計画は、保護者の理解と納得があることで、現場でより活かせるようになります。「わからないままサインしてしまった…」とならないよう、遠慮せずに質問することが大切です。
⑤計画後のモニタリングにも積極的に関わる
個別支援計画の作成後も「支援がうまくいっているか」「立てた目標は適切だったか」を振り返る場が設けられます。保護者もその場に出席し、家庭での変化や新たな困りごとなどを共有することで、次回の計画の見直しに反映することができます。支援員がひとりで作成するのではなく、「保護者も一緒につくりつづける」という姿勢が大切です。
個別支援計画の作成で迷ったら、AIAI VISITに相談を
AIAI VISITでは保育所等訪問をはじめとする障害福祉サービスを提供しています。子どもたち一人ひとりの発達状況や特性を丁寧にアセスメントのうえ、保護者の方の相談に乗りながら必要な支援計画を立てることができます。
個別支援計画の作成について悩む場合は、AIAI VISITを活用することも検討してみてください。
まとめ
個別支援計画は、障害のある子どもの特性や課題、本人・家族の希望や意向を汲んで作成されます。個別支援計画を正しく作成することは、子どもが自分らしく日常生活を送ったり、将来に向けて必要な力を身に着けたりするための支援につながります。また、障害福祉サービスの支援員や学校の教員、医療関係者など、子どもに関わる支援者間で支援方法を共有するための大切なツールでもあります。
家庭における子どもの様子や変化などの情報を共有することで、保護者も一緒に支援計画をつくっていけると良いでしょう。






