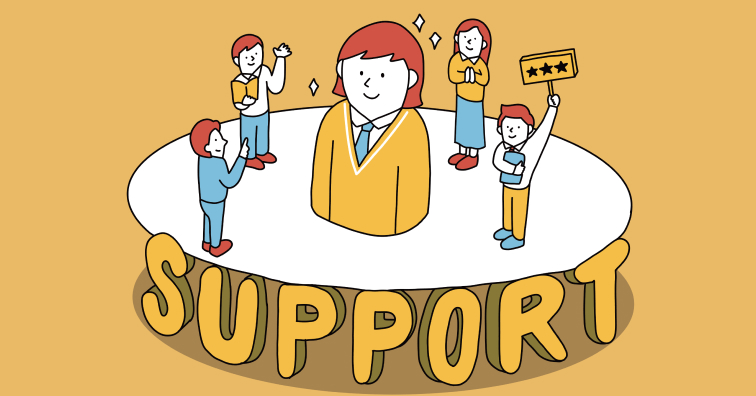相談支援事業所とは?種類や役割、利用の流れをわかりやすく解説
COLUMN

はじめに
「相談支援事業所って、そもそも何をしてくれるところ?」「自分の子どもに必要な支援がわからない…」発達障害などの障害のある子どもを育てるなかで、支援制度について悩む保護者は少なくありません。
本記事では、「相談支援事業所」の基本的な役割や種類、実際の利用の流れや費用、事業所の選び方までわかりやすく解説します。支援先に迷っている方が、必要な一歩を踏み出すためのヒントを得られる内容です。
相談支援とは
障害のある方やその家族が、地域の中で安心して暮らし続けるためには、さまざまな支えや情報が必要になります。そのときに頼れる存在のひとつが、「相談支援」です。
相談支援では、福祉サービスの利用に関する手続きのことはもちろん、「学校で困っていることがある」「将来、どんな進路が考えられるのか不安」など、日々の生活の中で感じる悩みについても相談することができます。
障害のある方の特性や状態、家庭の状況に合わせて、一人ひとりに合った支援の方向性を一緒に考えてくれるのが特徴です。「支援をどこから始めたらいいかわからない」と感じたときに、まず相談できる場所として、相談支援は多くのご家庭の支えになっています。
制度としての相談支援|厚生労働省の位置づけ
相談支援は、国が定める「障害者総合支援法」や「児童福祉法」に基づいた、正式な制度です。厚生労働省が制度を整備しており、障害のある方やその家族が必要な福祉サービスを適切に受けられるように支援体制がつくられています。
特に「計画相談支援」と呼ばれる仕組みでは、福祉サービスを利用する前に、「どんなサービスが必要か」「どう活用していくか」を整理した「サービス等利用計画」を作成することが求められています。これは、子どもの状態や家庭の状況をきちんと整理したうえで、無理のない形で支援につなげるための大切なステップです。
ほかにも、地域での暮らしを支える「地域相談支援」や、お子さまを対象にした「障害児相談支援」など、年齢や状況に応じた支援制度が用意されています。これらはすべて、市区町村から指定を受けた「相談支援事業所」の専門スタッフが担当しており、原則として無料で利用できます。
※参考
相談支援の種類
一言で「相談支援」といっても、制度上はさまざまな種類があり、それぞれ役割や対象が異なります。ここでは、主な相談支援の種類をわかりやすくご紹介します。お子さまやご家庭の状況に合った支援を見つけるための参考にしてみてください。
①基本相談支援
基本相談支援は、障害のある方やその家族が抱えるあらゆる悩みに対応する、もっとも基本的な相談支援です。福祉サービスのことに限らず、日常生活の困りごとや、進学・就職・人間関係といった幅広い内容を相談できます。
たとえば「学校生活での困りごとを誰かに相談したい」「まだ制度の利用は考えていないけれど、何から始めたらいいのかわからない」など、福祉サービスを利用していない段階でも、気軽に利用することができます。
相談先としては、市町村の障害福祉窓口や地域生活支援センターなどがあり、地域によって窓口の名称や機関が異なる場合もあります。
②地域相談支援
地域相談支援は、障害のある方が「地域で暮らしていくこと」を支えるための支援です。主に2つのタイプに分かれており、それぞれ目的が異なります。
②-1.地域移行支援
病院や福祉施設などで長期間生活していた方が、地域での暮らしに移行する際にサポートを行うのが「地域移行支援」です。
たとえば、アパートなどの住まい探しを一緒に進めたり、実際に体験入居に同行したりと、新しい生活を始めるための準備を支援してくれます。
②-2.地域定着支援
「地域定着支援」は、すでに地域で一人暮らしをしている障害のある方が、安心して生活を続けられるように見守る支援です。
たとえば「何日も連絡がつかなくなったときには訪問する」など、あらかじめ決めた対応に基づいて、日常の安全を見守る仕組みが用意されています。
③計画相談支援
計画相談支援は、福祉サービスを利用する際に必要となる「サービス等利用計画」を作成する支援です。
相談支援専門員がご本人や家族と面談を行い、困りごとや希望を整理したうえで「どのような支援が必要か」「どのようなサービスが適しているか」を計画としてまとめてくれます。
サービスを開始したあとも、定期的に支援内容を見直すことで、状況の変化に応じた対応ができる仕組みです。
③-1.サービス利用支援
福祉サービスを初めて利用する際には、この「サービス利用支援」が必要になります。利用者の希望や課題をもとに、必要なサービスや支援内容を具体的に整理して計画を立てていきます。
③-2.継続サービス利用支援
すでに福祉サービスを利用している方に対しては、「継続サービス利用支援」として、一定の期間ごとに支援内容を見直す仕組みがあります。サービスが適切に続けられているかを確認したり、必要に応じて内容の変更を検討したりする場として機能します。
④障害児相談支援
障害児相談支援は、18歳未満の障害のあるお子さまとその家族を対象とした支援です。お子さまが放課後等デイサービスや児童発達支援などを利用する際に、「サービス等利用計画」を作成したり、必要に応じて見直しを行ったりします。
④-1.障害児支援利用援助
放課後等デイサービスや児童発達支援などを利用するために必要な計画を作成します。お子さまの状態やご家庭の状況に応じて、どのような支援が必要かを整理して、適切なサービスにつなげていきます。
④-2.継続障害児支援利用援助
お子さまの成長や発達の変化に合わせて、支援内容を定期的に見直す支援です。「今のサービスが合っているか」「別の支援が必要になっていないか」といった点を確認しながら、より良い支援が継続できるよう調整していきます。
※参考
相談支援事業所の種類
相談支援を行う「相談支援事業所」には、目的や支援の内容によっていくつかの種類があります。それぞれの事業所には担当する役割があり、支援の内容や対象も少しずつ異なります。ここでは、代表的な3つの相談支援事業所の特徴についてご紹介します。
①一般相談支援事業所
「一般相談支援事業所」は、基本相談支援や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を担当する事業所です。
たとえば、「これから施設を出て地域で暮らしたいけれど不安がある」「近隣で一人暮らしを続けていけるか心配」といった相談に対して、地域での生活に移行するための準備や、生活を安定して続けるための見守り支援などを行います。
福祉サービスの利用に限らず、日常のちょっとした困りごとも相談できる場所であり、地域の障害福祉窓口や支援センターと連携しながら、身近な支援拠点として機能しています。多くの場合、特別な手続きなしで利用できるのも特徴です。
②特定相談支援事業所
「特定相談支援事業所」は、計画相談支援を専門に行う事業所です。障害福祉サービスを利用するためには、原則として「サービス等利用計画」を作成する必要があり、その計画づくりを担うのがこの事業所です。
相談支援専門員が、本人や家族の希望や課題を丁寧に聞き取り、必要な支援内容を整理した計画を提案します。サービス開始後も、計画通りに支援が行われているかを定期的に確認し、必要があれば内容の見直しや調整を行います。
つまり、福祉サービスを適切に活用するための“入口”となる、大切な役割を担う相談窓口です。
③障害児相談支援事業所
「障害児相談支援事業所」は、18歳未満の障害のあるお子さまを対象とした相談支援を行う事業所です。放課後等デイサービスや児童発達支援といった福祉サービスを利用する際に、必要な計画(障害児支援利用援助)を作成し、状況に応じて内容の見直し(継続障害児支援利用援助)も行います。
この事業所では、発達障害や学習障害など、特性の異なる子どもたちに合わせて支援内容を検討し、保護者と一緒に将来を見据えたサポートを考えていきます。子どもの状態に合った支援が受けられるよう、学校や関係機関と連携しながら支援を進めていくこともあります。
「どんな支援が必要かわからない」「成長に合わせてサービスを見直したい」といったときに、心強いパートナーとなる存在です。
※参考
相談支援事業所を利用するメリット・デメリット
相談支援事業所は、障害のあるお子さまやその家族が日々の生活を安心して送るための、心強いサポート機関です。一方で、利用にあたっては事前に知っておきたい注意点もあります。この章では、実際に相談支援事業所を利用することで得られるメリットと、あわせて理解しておきたいデメリットをバランスよくご紹介します。
相談支援事業所を利用するメリット
①制度やサービスの情報を整理してもらえる
障害福祉制度は内容が複雑で、すべてを自分で調べて理解するのは大きな負担になります。相談支援事業所では、専門知識を持った相談支援専門員が、家庭の状況やお子さまの状態に応じて、必要な制度やサービスをわかりやすく説明し、整理してくれます。
②福祉サービスの利用計画を一緒に立ててもらえる
実際にサービスを利用するためには、「サービス等利用計画」の作成が必要です。相談支援専門員は、希望や課題を丁寧に聞き取りながら計画を立て、手続きの代行や事業所との調整も行ってくれます。また、サービス開始後も定期的にフォローを受けられるため、長期的にサポートが続く安心感があります。
③不安を共有できる“第三者”としての役割
家族や学校以外にも、気持ちを共有できるプロがいることは、保護者にとって大きな心の支えになります。「こんなこと相談してもいいのかな…」ということでも、まずは話を聞いてもらえる場があることが、安心につながります。
④中立の立場からの助言が得られる
相談支援専門員は、学校や福祉事業所などと直接の利害関係がないため、保護者やお子さまの希望を第一に考えた客観的なアドバイスをしてくれます。関係機関との橋渡し的な役割も担ってくれるため、安心して相談できる存在です。
相談支援事業所を利用するデメリット
①担当者によって支援の質に差が出ることがある
相談支援専門員にも経験や得意分野に違いがあり、「この人に相談してよかった」と感じるケースもあれば、逆に相性が合わないと感じることもあります。可能であれば、初回相談時の印象や対応を確認し、納得のいく事業所を選ぶことが大切です。
②予約や対応に時間がかかることがある
地域によっては、相談支援事業所が混み合っており、初回面談までに時間がかかる場合があります。特に新年度や学期の変わり目などは相談件数が増える傾向があるため、早めに情報収集し、余裕を持って動くことがポイントです。
③すべての悩みに対応できるわけではない
相談支援事業所は福祉制度に関する相談を中心に対応していますが、学校内でのトラブルや医療的な判断など、分野外の内容には対応が難しいこともあります。必要に応じて、教育委員会や医療機関など、ほかの専門機関と併せて相談することも検討しましょう。
④計画相談支援が義務となる場合がある
一部の福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画の提出が必須となるため、「書類が多くて大変」「計画づくりに時間がかかる」と感じることもあるかもしれません。あらかじめ制度の流れを知っておくことで、準備がスムーズになります。
※参考
相談支援事業所利用の流れ・費用
「相談支援事業所を使ってみたいけれど、どうやって申し込めばいいの?」「お金はかかるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この章では、相談支援事業所を実際に利用する際の流れと、気になる費用負担についてわかりやすくご説明します。
相談支援事業所を利用するステップ
1.市区町村の障害福祉窓口に相談
まずは、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉課などに相談するのが一般的です。状況に応じて、適切な相談支援事業所を紹介してもらえる場合もあります。
2.相談支援事業所を選ぶ
紹介された事業所の中から、自宅からの距離や得意な支援分野などを参考にして、希望に合う事業所を選びます。インターネットなどを用いて自分で探して、直接連絡することも可能です。
3.初回面談・アセスメント
選んだ相談支援事業所で、相談支援専門員との初回面談(アセスメント)を行います。お子さまの状態やご家庭の状況、希望する支援内容について丁寧に聞き取りが行われます。この段階で、信頼関係を築くことがとても大切です。
4.サービス等利用計画の作成(必要な場合)
福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」と呼ばれる計画書の作成が必要な場合があります。専門員が相談内容をもとに必要な支援を整理し、計画を作成してくれます。
5.計画をもとにサービス提供が開始される
作成した計画をもとに自治体へ申請し、審査・支給決定が行われると、福祉サービスの利用が開始されます。利用開始後も、必要に応じて定期的な見直しやフォローアップが行われます。
利用にかかる費用負担
相談支援事業所を利用するにあたって、利用者が直接費用を支払うことは原則としてありません。計画相談支援にかかる費用も公費でまかなわれており、相談支援事業所が自治体に報酬を請求する仕組みとなっています。
基本的には無料ですが、まれに書類の郵送費や面談にかかる移動費など、実費が発生する場合があります。その際も、事前に説明されることがほとんどです。不安な場合は、初回の相談時に費用について確認しておくと安心です。
※参考
自分に合った相談支援事業所を見つけるために
相談支援事業所は全国に多数ありますが、「どこを選べばいいの?」「自分たちに合っているか不安」と感じる方も少なくありません。実際、事業所ごとに得意な支援内容や雰囲気が異なるため、相性の良い事業所を見つけることが大切です。
ここでは、相談支援事業所の探し方と、信頼できる事業所を選ぶためのポイントをご紹介します。
①相談支援事業所の探し方
まずは、お住まいの市区町村にある障害福祉課(福祉課や子ども家庭課など)に問い合わせてみましょう。地域の指定相談支援事業所の一覧を持っているため、信頼できる情報が得られます。
また、「〇〇市 相談支援事業所 一覧」と検索すると、各自治体のホームページや福祉情報サイトが表示されることがあります。また、WAM NET(福祉・介護情報の総合サイト)や、都道府県の福祉情報ページからも調べることができます。民間の支援団体が運営するポータルサイトも参考になります。
さらに、すでに病院や児童発達支援・放課後等デイサービスなどの支援機関と関わりがある場合は、その連携先として相談支援事業所を紹介してもらえるケースもあります。すでに信頼関係がある機関を通すことで、よりスムーズに話が進むことがあります。
②信頼できる相談支援事業所を見つけるポイント
①相談支援専門員の資格・経験を確認
事業所のウェブサイトやパンフレットを見て、「相談支援専門員」や「社会福祉士」「精神保健福祉士」などの資格を持つスタッフが在籍しているか確認しましょう。また、発達障害や知的障害など、関心のある支援分野にどれだけ詳しいか、経験年数や専門領域が記載されているとより安心です。
②面談・初回相談の雰囲気を重視
初回の無料相談や見学の際に、「話しやすい雰囲気かどうか」「こちらの話をじっくり聞いてくれるか」などを見てみましょう。対応の丁寧さや、相談スペースの清潔さ、個室や仕切りの有無など、居心地の良さも重要な判断材料です。
③提供サービスの幅と連携体制をチェック
地域移行支援や定着支援、障害児相談支援など、自分の家庭に必要なサービスが揃っているかを確認しましょう。また、他の福祉施設や医療機関と連携して支援してくれる体制が整っているかも、信頼度を測るポイントです。
④利用者や家族の声、事例紹介を参考に
事業所のウェブサイトや広報誌などに、保護者のインタビューや実際の支援事例が掲載されていることがあります。こうしたリアルな声は、その事業所の雰囲気や支援の手厚さを知る手がかりになります。
⑤アクセスの利便性や対応時間を確認
通いやすい場所かどうか、学校や病院からの移動のしやすさも重要です。あわせて、営業時間や休日対応の有無など、ライフスタイルに合った事業所を選びましょう。
※参考
相談支援事業所の利用に迷ったら。AIAI VISITに相談してみませんか?
「相談支援事業所の仕組みはなんとなく分かったけれど、実際にどこへ相談すればいいのか分からない」「自分の子どもに合った支援が何か、まだ判断がつかない」と感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、AIAI VISITの無料相談サービスをぜひご活用ください。
AIAI VISITでは、発達障害のあるお子さまとその家族を対象に、保育所等訪問支援事業を行なっています。発達障害のあるお子さまの支援に向けて、「計画相談支援ってうちも必要?」「障害児相談支援ってどんな内容?」といった疑問にもお答えします。
相談先に迷ったとき、不安を抱えたまま一人で悩まずに、まずは一度お気軽にご相談ください。あなたとお子さまに合った支援のかたちを一緒に考えます。
まとめ
相談支援事業所は、障害のあるお子さまやその家族が、地域で安心して暮らしていくための大切なサポート拠点です。制度の内容は一見難しく感じられるかもしれませんが、まずは「困ったときに話を聞いてくれる人がいる」ということを知っておくだけでも、気持ちが少し軽くなるはずです。
本記事では、相談支援の基本的な仕組みや種類、事業所ごとの役割、利用の流れ、費用、そして選び方のポイントまでを解説してきました。
とはいえ、実際に「どこに相談したらいいのか」「うちの子に必要な支援は何か」と迷うこともあるでしょう。そんなときは、一人で抱え込まず、AIAI VISITの無料相談など、身近なサポートを活用してみてください。
最初の一歩を踏み出すことで、子どもにとっても、家族にとっても、より良い支援の選択肢が見えてくるはずです。