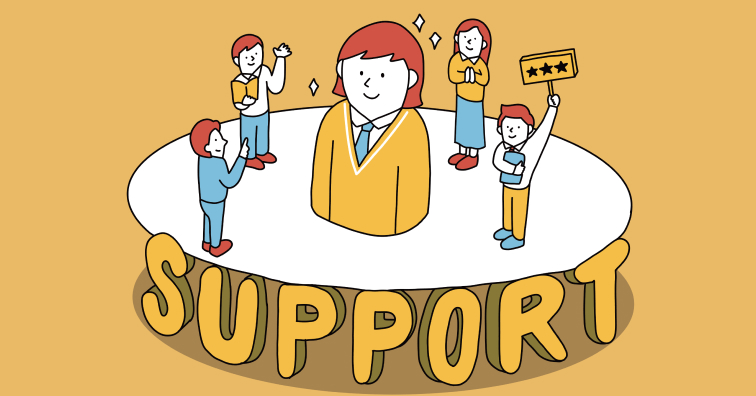障害者雇用とは?一般雇用との違いやメリット・デメリットなど、発達障害の子どものための就職ガイド
COLUMN

はじめに
「発達障害のある子どもは、将来どんな仕事に就けるんだろう」「障害者雇用ってよく聞くけど、うちの子にも関係あるの?」
そんな不安や疑問を感じている保護者の方は、決して少なくありません。
障害のある方が自分らしく働けるように設けられた「障害者雇用」という制度は、発達障害のあるお子さんにとっても進路の一つになり得るものです。
でも、「一般雇用との違いがわからない」「どうやって支援を受ければいいの?」といった壁にぶつかることも多いはず。
この記事では、障害者雇用の基本的な仕組みや対象者、就職活動を進めるうえでのポイント、そして利用できる支援機関について、やさしく丁寧に解説しています。
お子さんにとって最適な働き方を考えるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
障害者雇用とは?
障害者雇用とは、障害のある方がその人らしく働けるように、企業が環境や働き方を工夫しながら雇用する制度のことです。一人ひとりの希望や能力、特性に応じた働き方を実現することで、障害のある方が社会の一員として活躍できることを目指しています。
この制度は「障害者雇用促進法」に基づいて定められており、企業には一定割合の障害者を雇用することが義務づけられています。これを「法定雇用率」と呼び、2024年度現在、民間企業の場合は2.5%です(従業員40人以上の企業が対象)。この割合は今後も段階的に引き上げられ、2026年度には2.7%となる予定です。
障害者雇用の状況
厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障害者の雇用者数は約65万人と、過去最高を更新しました。法定雇用率の達成企業の割合も年々増加しており、2024年時点で50.1%の企業が基準を満たしています。
中でも精神障害者の雇用が大きく伸びており、全体の約4割を占めるようになっています。これは、発達障害を含む精神障害の方への理解や配慮が広がってきたことの表れともいえます。企業も「誰もが働きやすい職場づくり」に力を入れるようになってきているのです。
障害者雇用制度の歴史
障害者雇用制度のはじまりは、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」までさかのぼります。戦後の日本では、傷病兵や障害を負った人々の社会復帰が大きな課題となっており、国としても就労支援が必要とされていました。
その後、1976年には「障害者雇用促進法」として法律が改正され、民間企業にも障害者を雇う義務が明記されました。当初は身体障害者が対象でしたが、1998年から知的障害者、そして2018年からは発達障害を含む精神障害者も制度の対象となっています。
さらに2016年には法改正があり、企業には障害者に対して「差別をしてはいけないこと」「合理的配慮をすること」が義務づけられました。これは、「みんなが働きやすい職場をつくる」という社会全体の意識の変化を反映した重要なステップです。
障害者雇用の対象者
障害者雇用は「障害のある方が安心して働くための制度」ですが、誰もが自動的に対象になるわけではありません。まずは、「どのような条件の人が障害者雇用の対象になるのか」を知っておくことが大切です。
原則として、障害者雇用の対象となるのは「障害者手帳を持っている人」です。障害者手帳には大きく分けて3つの種類があります。
・身体障害者手帳
病気やけがなどで、視覚・聴覚・肢体・内部機能などに一定以上の障害がある人に交付されます。たとえば、手足の動きに不自由がある、人工透析が必要な持病があるなどが該当します。
・療育手帳
知的障害(知的発達症)がある方を対象に、知的機能や日常生活の状況に応じて交付されます。都道府県や自治体によって名称が異なる場合がありますが、全国的に共通して使える手帳です。
・精神障害者保健福祉手帳
統合失調症やうつ病、双極性障害、発達障害など、精神障害のある方に交付されます。発達障害のある方がこの手帳を取得するケースも増えており、障害者雇用枠での就職を目指す際に活用されています。
障害者手帳を持っている方は、「障害者雇用枠」の求人と「一般雇用枠」のどちらにも応募することが可能です。たとえば、職場での配慮や支援を受けながら安定した働き方をしたい場合は、障害者雇用枠が向いていることが多いでしょう。一方で、職種の幅や給与条件を重視する場合は、一般雇用枠に挑戦する方もいます。
また、必ずしも手帳を持っていなければ応募できない、というわけではありません。特に精神障害や発達障害のある方の場合は、医師の診断書などを提出することで障害者雇用枠の求人に応募できるケースもあります。これは企業側の判断によるため、求人票や企業の採用ページに記載された条件をよく確認することが大切です。
障害のあるお子さんの進路を考えるうえで、「手帳の有無」や「診断書の活用方法」などを早めに把握しておくと、将来の選択肢が広がります。また、進学や就労のタイミングで手帳の取得を検討する際は、医療機関や自治体の相談窓口と連携しながら進めると安心です。
障害者雇用と一般雇用のメリット・デメリット
障害のあるお子さんの将来を考えるとき、「障害者雇用で働くべきか、一般雇用を目指すべきか」という悩みは避けて通れません。それぞれにメリット・デメリットがあるため、本人の特性や希望、将来像に応じて選択していくことが大切です。ここでは両者の違いをわかりやすくご紹介します。
障害者雇用のメリット
障害者雇用の最大の特徴は、障害のある方が無理なく働けるように配慮された職場環境が整っていることです。企業には法律により、障害に対する合理的配慮を行う義務があるため、業務内容や勤務時間、通勤方法などの調整をしてもらいやすい傾向があります。
また、得意なことを活かす仕事に集中できるよう、業務内容を限定してくれる場合もあります。加えて、ジョブコーチ制度や就労支援機関のサポートを受けながら働くことも可能で、就労が初めての方でも安心してスタートできる仕組みが整っています。
障害者雇用のデメリット
一方で、障害者雇用にはいくつかの課題もあります。まず挙げられるのが給与水準の低さです。一般雇用に比べて時給や月給が低く設定されているケースもあり、生活の自立には別の支援を併用する必要がある場合もあります。
また、企業によってはキャリアアップの機会が限られている可能性もあります。昇進や昇給の制度が整っていなかったり、障害者枠での雇用においては「補助的な業務」にとどまってしまう可能性もあります。職種や業務内容が限定的なため、本人の希望がすべて叶えられるとは限らない点は注意が必要です。
一般雇用のメリット
一般雇用では、他の人々と同じ条件で働くことが前提となるため、給与や待遇面での不公平感が少ない傾向にあります。実力次第で昇進や昇給といったキャリアアップの道も開かれやすく、職種や配属先もより多様な選択肢から選ぶことが可能です。
「自分の力でどこまでできるかチャレンジしたい」「興味のある仕事に就きたい」といった希望を持つ方にとっては、一般雇用という選択が大きな可能性につながることもあります。
一般雇用のデメリット
ただし、一般雇用では障害に対する配慮が十分に受けられないこともあり得ます。企業側に障害理解がない場合、適切なサポートが得られず、無理をしてしまうことも。特に発達障害など「外見から分かりづらい障害」の場合、周囲の理解が得られにくいという壁にぶつかることがあります。
また、職場の環境や人間関係にうまくなじめず、ストレスを抱えてしまうケースもあります。本人の自己理解やストレス対処能力がまだ十分でない場合は、無理に一般雇用を目指すことで逆に心身の負担が大きくなることもあるため、慎重な検討が必要です。
どちらの雇用形態が良い・悪いということではなく、「子どもにとって、どちらが今の段階で無理なく力を発揮できるのか」という視点で考えることが大切です。
必要に応じて、専門家や支援機関と一緒に進路を整理してみましょう。
発達障害のある子どもの就職を考える時のポイント
発達障害のある子どもが社会に出て働くというのは、親にとっても大きな関心ごとの一つです。「この子に合った働き方って?」「就職できるの?」と、不安は尽きないもの。そんなとき、就職というゴールを焦るよりも、まずは一歩ずつ、子どもの“今”を大切にしながら進めていくことが大切です。ここでは保護者の立場から考えたい、5つのポイントをお伝えします。
①まずは子どもの特性を理解する
発達障害と一言で言っても、その特性や困りごとは本当に人それぞれ。注意力が続きにくい、音に敏感、得意なことには集中できるなど、子どもの「苦手」や「得意」をしっかりと把握することが、将来の職場選びにも大きく影響します。まずは家庭での様子や学校での出来事を通じて、子ども自身の特性を見つめ直してみましょう。
②子どもの意思を尊重する
つい親が「安定していて働きやすい会社がいい」と先回りしてしまうこともありますが、何より大切なのは「子ども自身のやってみたいこと」を聞くことです。どんなに配慮された職場でも、本人が興味を持てない仕事では長続きしにくいもの。小さな夢や好奇心を大切にしてあげることで、本人の自己肯定感や働く意欲にもつながります。
③子どもの特性に合った働き方を考える
たとえば、人と話すのが苦手でも、モノづくりやパソコン作業が得意なら、裏方の仕事やIT系の職種も選択肢に入ってきます。逆に、人と関わることが好きな子なら、接客や販売の仕事でその力を活かすこともできるでしょう。就労支援の場では、特性に応じた職種選びの相談にも乗ってもらえるので、無理なく活躍できる場を探すことができます。
④就職に向けた準備は早めにスタートする
就職準備は、いざ卒業を迎える前から始めておくと安心です。特に高校進学の段階で、「就職に強い学校」を選ぶという視点を持つのも一つの方法です。
たとえば、実践的なスキルを学べる高等専門学校や高等専修学校など、発達障害のある子どもにも適した進路が増えています。具体的な学校の選び方については、関連記事をご参照ください。
⑤現在在籍している学校や支援機関に相談する
就職について考える際、保護者だけで抱え込む必要はありません。担任の先生や特別支援教育コーディネーター、就労支援を行っている福祉機関など、相談できる相手はたくさんいます。学校内での様子を共有しながら、就労に向けたスモールステップを一緒に考えてくれる専門家の存在は、親にとっても大きな支えになるはずです。
「どんな職場が合っているのか」「うちの子にできる仕事はあるのか」と悩むときこそ、身近なサポートを上手に使いながら、子どもの将来に寄り添っていきましょう。
障害者雇用での就職を考えた時に活用できる機関・制度
障害のあるお子さんの就職を考えるとき、「誰に相談すればいいの?」「どんなサポートが受けられるの?」と迷う方も多いと思います。そんなときは、専門的な知識や支援体制を持つ機関を活用するのがおすすめです。ここでは、障害者雇用を希望する際に役立つ主な相談先をご紹介します。
①公共職業安定所(ハローワーク)
障害者雇用に関する最も身近な相談窓口の一つが、ハローワーク(公共職業安定所)です。各地のハローワークには「専門援助窓口」や「障害者専門の就職支援員」が配置されており、障害のある方が安心して働けるよう、求人の紹介や就職相談を行っています。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断や支援学校の紹介で相談が可能なケースもあります。履歴書の書き方や面接の練習など、実践的なサポートを受けられるのも大きな魅力です。
②地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害のある方が職業生活を送るために必要な支援を提供する専門機関です。各都道府県に設置されており、心理職や職業カウンセラーなどの専門スタッフが在籍しています。
職業準備性(働くためのスキルや生活習慣)を測定したり、本人の特性に応じた職場実習の提案をしてくれるのが特徴です。また、企業との間に立って「合理的配慮」をどう実現するかを調整する役割も担っています。就労へのステップをじっくり整えたい方におすすめです。
③就労移行支援
就労移行支援は、障害のある18歳〜65歳未満の方が一般企業への就職を目指すために、最長2年間、通所しながら支援を受けられる福祉サービスです。ビジネスマナーの習得、軽作業やパソコンスキルの訓練、職場体験、就職活動の支援まで幅広くカバーしています。
発達障害のある方に特化した支援を行っている事業所もあり、個々の特性に応じた指導を受けられるのもポイント。また、就職後も定着支援(=職場に慣れるまでのフォロー)を行ってくれるので、初めての就職でも安心して働き続けられる体制が整っています。
④学校などで行っている就職支援
特別支援学校や高等学校でも、進路指導や就職支援が行われています。進路指導担当の先生や特別支援教育コーディネーターが、子どもの特性を理解したうえで、進学・就職に向けた個別の支援計画を立ててくれることもあります。
また、学校によっては企業とのマッチングや職場実習の機会を設けているところもあります。学校生活の中で自然と働く経験を積むことができるのは、子どもにとっても大きな自信になります。
不安なことや迷いがある場合は、まずは学校の先生に相談するところから始めてみましょう。家庭と学校が連携してサポートすることで、就職への道がぐっと現実的になります。
このように、就職に向けて利用できる支援機関はたくさんあります。
「誰かに頼ってもいいんだ」と思えることが、親子にとっての第一歩になるかもしれません。
子どもの就職に悩んだら。AIAI VISITに相談してみませんか?
「発達障害のある子どもが、将来どんなふうに働けるようになるんだろう」「今のうちにできることは何かあるのかな?」
そんな不安や疑問を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。
AIAI VISITは、就職支援そのものを行っているわけではありませんが、子どもたちの特性を理解し、その子らしく成長できる環境づくりを支援するため、保育所等訪問支援のサービスを提供しています。
お子さんが集団生活の中でどんなところに困りごとがあるのか、どうすれば安心して過ごせるのかを見つけ、保育所等訪問支援というかたちで現場に出向いてアドバイスやサポートを行っています。進路や将来の選択に悩むときも、まずは今の子どもの姿をしっかり知ることが、将来の土台づくりにつながります。
「何から始めればいいか分からない…」そんな時こそ、AIAI VISITに相談してみてください。
保護者の皆さまの気持ちに寄り添いながら、一緒にお子さんの“これから”を考えていきます。
まとめ
発達障害のある子どもの就職について考えるとき、「何が正解か分からない」「うちの子に合った働き方って?」と迷ってしまうことは少なくありません。
でも、障害者雇用という制度が整ってきた今だからこそ、無理をせず、その子の特性や希望に合った道を選ぶことができるようになってきました。
大切なのは、「障害があるからこの道しかない」と決めつけるのではなく、
子ども自身の想いや得意なことに耳を傾け、どんな働き方が“その子らしい”のかを一緒に考えていくこと。
そして、親だけで悩まず、専門家や支援機関の力を借りながら進んでいくことが、より良い未来への近道になります。
AIAI VISITでは、発達障害のあるお子さんの進路や就職に関する無料相談を行っています。
「どこに相談すればいいかわからない」「何から始めればいい?」という段階でも大丈夫。
まずは気軽に、話してみることから始めてみませんか?