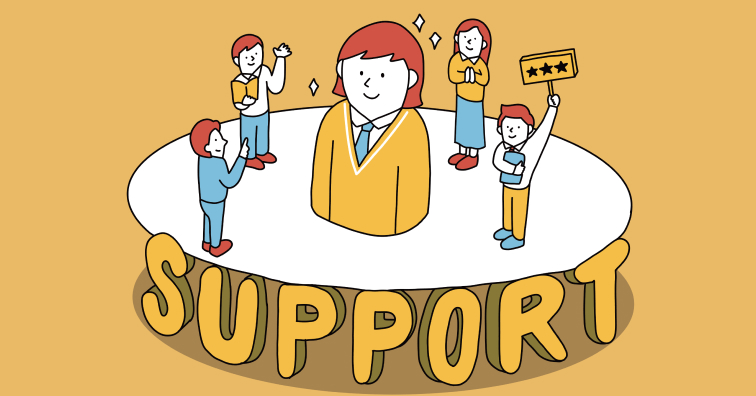発達検査とは?具体的な内容や種類、受けられる場所や発達検査を受けたあとのステップなど、気になるあれこれを解説します!
COLUMN

発達検査とは、子どもの心身の発達状況を調べる検査のことです。言語や運動などさまざまな領域の発達度合いを測定することで、子どもの特性を理解したり支援の方針を立てたりするときに役立ちます。この記事では発達検査の種類や内容、受けられる場所、検査の意義について詳しく解説するとともに、発達検査を受けた後、どのような行動につなげればいいのかを解説します。
発達検査とは?
発達検査とは、子どもの心身の発達の状況を調べる検査のことです。さまざまな方法で認知、言語、社会性、運動などさまざまな領域の発達度合いを客観的に測定します。
発達検査にはいくつも種類があり、子どもの状況や年齢によってどの検査方法を用いるかが異なります。
発達検査の目的
発達検査の目的は、子どもの特性や発達度合いを明確にすることで、支援や療育の手がかりを得ることです。子どもの特性や発達状況はひとり一人異なるため、適切な支援や療育にはその子どもの特性や発達度合いの把握が必要だからです。
例えば発達検査を通して子どもの強みや特性を知ることで一人ひとりに合う支援方法や学び方を考えること、その子どもがすごしやすい環境や配慮を用意することもできます。
見た目ではわかりづらかった本人の困りごとが、検査の結果をとおして明らかになることもあります。検査結果を学校や家庭での関わり方に生かすことで、子どもの困りごとを軽減してすごしやすくすることができるほか、客観的な検査結果は、支援機関や園・学校、家庭など、さまざまな場で子どもに関わる大人たちがともに支援の方向性を定め、支援計画を作成するためにも活用されます。
発達障害や発達の遅れを早期に発見することで、適切な支援や療育に速やかにつなげることも可能になります。
発達検査と知能検査の違い
発達検査を受けるとき、知能検査も一緒に受けることを勧められる場合があります。発達検査と知能検査の違いを大きく3つ紹介します。
1つ目は、調べる領域の違いです。発達検査では知能に加えて社会性や運動能力、適応能力など幅広い領域を測定します。対して知能検査では、主にIQ(知能指数)や認知能力を評価します。
2つ目は、検査が適用される年齢の違いです。発達検査は乳幼児から大人まで幅広い年齢の人が対象で、早いものでは適用年齢が0歳0ヶ月から設定されています。対して知能検査は主に学齢期の子どもが対象で、早いものでも適用年齢は2歳からです。
3つ目は、検査結果の利用目的の違いです。発達検査の結果は主に療育や支援計画作成のために利用されますが、知能検査は学業能力や、特性を測るために利用されます。
発達検査の意義|発達検査=発達障害の診断ではない
発達障害の診断には、医師による総合的な評価が必要です。発達検査の結果は判断材料のひとつとして使われるものの、発達検査=発達障害の診断ではありません。
発達検査の意義は、子どもの発達状況や特性を把握して支援や関わり方に生かすための情報であるといえます。検査結果は子どもの課題だけではなく、強みや、それを生かした学び方や環境を知るための手がかりにもなります。
主な発達検査の種類と特徴
発達検査にはさまざまな種類があり、種類によって検査結果の表現方法や測定領域、対象年齢などが異なります。どの発達検査を受けるべきか、専門家に相談してみてください。担当する医師や実施機関ごとに扱う検査も異なるため、受けたい検査がある場合は事前に問い合わせるとよいでしょう。
ここでは「新版K式発達検査」と「津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法」「日本版デンバー式スクリーニング検査」について紹介します。
① 新版K式発達検査
- 対象年齢:生後100日~成人(特に幼児~小学生向けに多く用いられる)
- 検査方法:「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」の3領域を評価
- 形式:個別検査、行動観察
新版K式発達検査は、年齢において一般的と考えられる行動や反応と、対象児者の行動や反応が合致するかどうかを評価する検査です。子どもの日常生活に密接した課題をとおして、子どもの行動を観察します。それぞれの領域の得点から「発達年齢」と「発達指数」を算出することが可能です。
② WISC(ウィスク)検査
- 概要
- 知能指数(IQ)を測定する検査
- 言語理解、視覚・空間認知、作業記憶、処理速度などの領域を評価する
- 対象年齢
- 5歳~16歳11ヶ月
- 特徴
- 認知能力を多面的に評価し、学習支援や特別支援教育の計画に活用されることが多い
③ 乳幼児精神発達診断法(津守・稲毛式)
- 対象年齢:生後3ヶ月~7歳頃が目安
- 検査方法:「社会性」「運動」「生活習慣」「言語・理解」「探索・操作」の5領域を評価。
- 形式:保護者など子どもの養育者に個別面接
「運動」「探索」「社会」「生活習慣」「言語」の5領域の438の質問項目から構成されています。「1~12ヶ月まで」「1~3歳まで」「3~7歳まで」の3種類の質問紙を用いて検査・面接を行います。5領域ごとに「発達年齢」が算出されます。
④ 日本版デンバー式スクリーニング検査
- 対象年齢:生後1ヶ月~6歳頃が目安
- 検査方法:「個人-社会」「微細運動-適応」「言語」「粗大運動」の4分野を評価
- 形式:個別検査、行動観察
アメリカで作られたデンバー式発達スクリーニング検査の日本版です。発達の遅れを早期に発見し、専門的な検査の必要性を判断する際に用いられます。
それぞれの行動について25%~90%の達成率を示す標準枠を階段状に図示します。標準枠のなかで色付けされている部分は、75~90%の達成率を表しており、この標準枠と実際の年齢線を比較しながら、同年齢のこどもと同様の発達段階にあるかどうかを判定します。
発達検査の具体的な内容
発達検査の内容は、実施する施設や検査種類によって異なります。そのため検査を受ける前に、目的や対象年齢に適した内容であるかを事前に確認することが必要です。ここでは一般的な発達検査の内容について、例をあげて説明します。
① 認知・知能
子どもの認知的な強みや課題を特定し、学習や生活での適応支援に役立てることを目的として検査を行います。
発達検査の内容例
- パズルや図形模写:視覚的認知力と問題解決力を確認する
- 数字を覚えて再現するテスト:記憶力と注意力を測定する
② 言語
発達検査の内容例
- 単語や文章の繰り返し:言語記憶や聴覚的理解を確認する
- 絵を見てストーリーを作る課題:表現力や語彙力を測定する
③ 社会性
社会的な場面での行動特性を把握し、適応行動を支援することを目的として検査を行います。
発達検査の内容例
- ロールプレイ(例えば、買い物をするシーンの再現):社会的な行動の評価
- 会話のやりとりの模擬テスト:コミュニケーション能力を測定
④ 姿勢・運動
運動発達の遅れや課題を特定し、理学療法や運動療育の計画に活用することを目的として検査を行います。
発達検査の内容例
- 積み木を積む:手先の器用さと集中力を測定
- ジャンプや走る課題:全身運動能力を評価
発達検査を通して何が分かる?
発達検査の結果からどのようなことがわかるのか、解説します。
① 発達プロフィール
検査項目と月年齢を軸にして、発達領域別の特徴を折れ線グラフで表現したものです。例えば「言語」「社会性」「運動」といった領域それぞれの発達状況を可視化します。発達プロフィールは発達障害の診断の参考に使われるほか、得意と苦手の凸凹が明らかになるため支援計画を立てるのにも使用されます。
② 発達年齢
発達年齢は、その子どもの発達の状態が、平均的な年齢においてどの段階に相当するのかを測定した結果です。例えば、6歳児が「言語の発達年齢は7歳相当、運動の発達年齢は5歳相当」と評価されるケースなどがあります。実際の年齢と発達年齢のギャップを把握し、支援計画を立てる際に役立ちます。
③ 発達指数
発達年齢と実際の年齢である生活年齢(Chronological Age:CA)との比率を求めたものが発達指数(Developmental Quotient:DQ)です。発達年齢と実際の年齢が同じ場合、発達指数が100という結果になります。発達状況を数値で客観的に説明できることから医療や教育機関での共有にも活用しやすいという面もありますが、発達指数はあくまでものさしのひとつです。普段の生活の様子などさまざまなことを総合して発達状況を把握していきます。
④ 検査報告書
検査結果をまとめた「検査報告書」を検査後に受け取ることができます。検査報告書には、検査結果の数値、検査結果からいえること、日常生活上配慮が必要なこと、医療機関・支援機関でのサポート内容の提案などが記載されます。子どもが必要としている支援を把握したり、個別の支援計画を立てる際に役立ちます。
発達検査はどこで受けられる?主な実施機関や費用の目安
発達検査が受けられる機関について解説します。
① 医療機関
小児科、児童精神科、発達外来を持つ総合病院や専門クリニックなどで発達検査を受けることができます。
医師による診断が可能で、必要に応じて治療や医療的なサポートも受けられることがあります。また、医療保険が適用される場合には費用を抑えることができます。
ただ多くの医療機関では検査の予約が取りづらく、数ヶ月待ちになることも少なくありません。また、診断を重視するため、支援計画への具体的な提案が不足する場合があります。
医療機関での検査を希望する場合は、かかりつけ医に相談して必要に応じて紹介状を書いてもらいましょう。
② 公的機関
児童相談所、発達障害支援センター、市区町村の福祉センターなどの公的機関でも発達検査を実施している場合があります。
費用が無料または低額で済むケースが多いこと、地域の支援機関と連携しやすいことが特徴です。ただし、該当機関に医師が在籍しないと医療的な診断は行えない場合や、検査結果のフィードバックが簡易的な場合があります。まずはお住まいの自治体の窓口で相談してみてください。
③ 民間機関
民間の発達支援センターや療育施設などで発達検査を受けられる場合があります。医療機関や公的機関と比べると比較的予約をとりやすく、子どもの状況にあわせた個別対応ができる場合が多いです。ただし医師が在籍しない場合は医療的診断を行うことができない、費用が比較的高額になることが多いという特徴もあります。機関によってさまざまなので、気になる場合は直接問い合わせて、検査の内容や資格を持った専門家が検査を実施しているのかどうかを確認してみてください。
費用の目安は1.5万円〜4万円程度
発達検査の費用は、実施機関や地域、検査の内容によって異なります。具体的な検査費用の目安は下記の通りです。
- 医療機関:5,000円〜2万円(保険適用の場合)
- 公的機関:無料〜1万円程度
- 民間機関:3万円〜4万円程度
発達検査に健康保険が適用されるかどうかは、事前の確認が必要です。
発達検査の結果はどう活用する?
発達検査でわかったことをどのように活用し、行動につなげていけば良いのかを解説します。
① 子どもの強みと課題を理解する
発達検査では、課題とともにその子どもの得意なことや強みも明らかになります。例えば、言語能力が高い場合はそれを生かした学び方や遊びから課題へアプローチしたり、強みを伸ばしたりすることにもつながります。
② 専門家と相談する
発達検査の結果を踏まえて専門家と相談し、今後の支援方針を立てることに役立ちます。検査をとおして子どもの強みや課題・特性についての情報が増えるため、専門家に子どものことを共有しやすく、方針を立てやすくなります。
③ 発達支援(療育)など、支援計画の策定に活用する
発達検査の結果をふまえて、個別の支援計画(IEP)などが作成されます。学校や療育施設・医師などと発達検査の結果を共有することで、子どもの発達に応じた具体的な支援計画を立てることができます。家庭でもできる支援方法を日常的に取り入れやすくなるともいえるでしょう。
④ 定期的な見直しや調整に活用する
子どもの状況は、日々変化します。発達についての課題や日常に起きる困りごとが変わってきたとき、支援の方針が合わなくなってきたときには、支援計画を見直すことも必要です。一度受けて終わりではなく、定期的に検査を受けることで、子どもの成長状況をチェックすることもできます。
発達検査の結果をどう受け止めればいい?発達検査に関するよくある質問(Q&A)
Q1:発達検査で思った通りの結果が出なかった場合、どうすればいい?
発達検査の結果は、あくまでも「現在の状況」を示しているだけで、将来的な成長を示唆するものではありません。
大切なのは、検査結果を参考にしたうえで子どもに必要な支援につなげていくことです。専門家にも相談しながら、検査結果の受け止め方や今後の支援への生かしかたを考え、子どもの成長を支えるために行動していきましょう。
Q2:発達検査で「発達障害」と診断される?
発達検査の結果のみで「発達障害」と診断されるわけではありません。発達検査は子どもの発達状態を把握するための「評価」であり、診断が必要な場合には、医師の診断やさらに専門的な検査が必要です。
発達障害の診断が必要かどうかが気になる場合は発達検査後に医師や専門家と相談し、次のステップを決定すると良いでしょう。
Q4:発達検査の結果は、子どもにどのように伝えるべき?
子どもに発達検査の結果を伝えるかどうかは、年齢や理解度に応じて配慮が必要です。検査結果を良い・悪いで伝えるのではなく、「できることがたくさんある」「今後支援を受けながら成長していこう」というメッセージを伝えると良いでしょう。
子どもが発達支援を前向きな気持ちで受けられるような声かけを大切にしてみてください。
Q5:発達検査は再検査になることがある?
発達検査はそのときの子どもの状態を測るものであり、「普段家でできていることが、検査の場面ではできなかった」といった理由で再検査になることはありません。
ただし発達は時間とともに変化するため、定期的に再評価を行い、支援が効果を上げているかを確認することが推奨されています。発達に気になる点がある場合や支援の方向性を再検討する必要があると感じた場合には、再検査を受けることで、より適切な支援を受けるための参考になるでしょう。
必要に応じて専門家と相談し、適切なタイミングで検査を受けることをおすすめします。
まとめ
発達検査を受けることで、子どもの発達における課題や強み、特性について客観的な情報を得ることができます。結果は、子どもの状況に応じて必要な配慮や支援を考えることに役立つだけではなく、専門家に相談しながら支援を進めるうえでも大切です。どの検査方法や検査場所を選ぶのかどうか迷ったときには、発達検査を行う機関や民間施設などに問い合わせて相談してみてください。