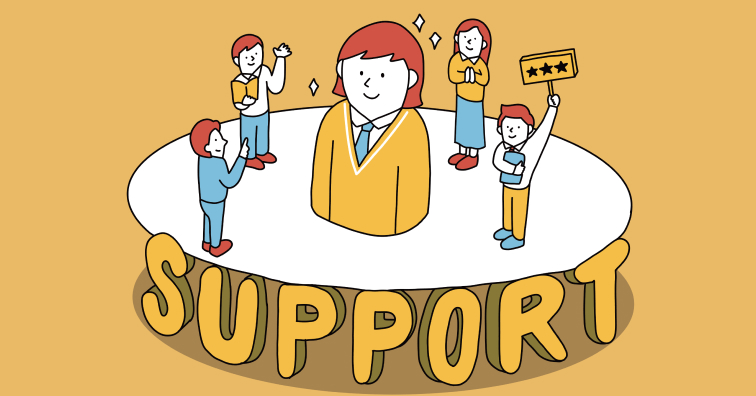「てんかん発作」や「チック症状」とは?症状や発作の原因、対処方法とは?
COLUMN

「てんかん」や「チック」といった神経系の症状は、保護者にとって大きな心配事の一つです。しかし、これらの症状に対する正しい理解と適切な対応を行うことで、子どもたちの生活の質を大きく向上させることができます。このコラムでは、てんかんやチックの基礎知識から原因、症状、治療法、さらには子どもとの関わり方まで、知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
「てんかん」とは?
てんかんは、脳の神経細胞で突然発生する強い電気的な興奮により繰り返し発作を引き起こす慢性的な脳の状態です。世界保健機関(WHO)は、てんかんを脳の神経細胞に異常な電気活動が生じ、多様な症状を引き起こす疾患と定義しています。日本ではおよそ100万人がてんかんと診断されており、決して珍しい病気ではありません。
また、0歳から18歳頃までに発症するてんかんを小児てんかんと言います。この時期に発症するてんかんは1回の脳波検査では診断がつかないこともあります。
「てんかん」の原因は?知っておきたい要因
てんかんの原因はさまざまで、完全に解明されているわけではありません。以下に主な原因を挙げます
- 脳血管障害:脳出血や脳梗塞など。
- 出生時のトラブル:出産時に脳にダメージが生じた場合。
- 感染症:ウイルスや細菌による影響。
- 遺伝子の変異:特定の遺伝的要因。
- 先天的な代謝異常:代謝に関する問題。
- 自己免疫の異常:免疫システムの影響。
原因が特定できないてんかんは「特発性てんかん」として分類されます。約6割が「特発性てんかん」というデータもあります。乳幼児や高齢者に発症しやすい特徴もあり、特に3歳以下と60歳以上で発症率が高くなることが知られています。
「てんかん」の発作のタイプ別特徴
てんかん発作は、脳の神経細胞の過剰な興奮が引き起こす症状で、現れ方はさまざまです。主な発作は以下の3つに分類されます。
① 部分発作(焦点発作)
脳の特定の部分が興奮することで起こります。症状は発作が起こる部位によって異なります。
単純部分発作(意識保持)
- 運動機能の障害 手足や顔の一部がピクピクする、片側の手足のしびれなど
- 視覚や聴覚の異常 光が見える、音が聞こえるなど
- 精神症状 突然の恐怖感や懐かしさを感じるなど
- 自律神経症状 異常な味や臭いを感じる、急な発汗など
複雑部分発作(意識減損)
- 意識が曇り、周囲の状況を理解できない
- 無意味な動作の繰り返し(手をたたく、口をもぐもぐさせるなど)
- 一点を見つめる
- 突然動作が停止する
② 全般発作
脳全体が同時に興奮する発作です。以下のような症状がみられます。
- 突然意識を失い倒れる。
- 全身のけいれん。
- 数秒間意識を失う欠神発作。
- 全身が一瞬ピクッとするミオクロニー発作。
- 全身の力が抜けて倒れる脱力発作。
③ 起始不明発作
発作の開始部位や広がりが特定できないタイプです。
部分発作(焦点発作)と全般発作のどちらとも判断できないものがこれに当たりますが、診断が難しく、さらに詳細な検査が必要になる場合があります。
てんかんの診断と治療法を解説
てんかんは、適切な診断と治療を通じて発作を抑え、生活の質を高めることが可能です。以下では、診断の流れと主な治療法について解説します。
てんかんの診断
てんかんの診断には、以下の検査を組み合わせて行います。
- 問診:発作の状況や既往歴を詳細に確認。
- 脳波検査:発作時の脳の電気活動を記録。
- 画像検査:MRIやCTで脳の状態を確認。
- 血液検査など:関連する疾患や異常を調べる。
特に脳波検査は、てんかんの診断において重要です。
てんかんを治療する上での選択肢
てんかんは、適切な診断と治療を通じて発作を抑え、生活の質を高めることが可能です。以下では、診断の流れと主な治療法について解説します。
1. 薬物療法
抗てんかん薬を使用して発作をコントロールします。患者の約60〜70%で発作が抑制されると言われています。基本的には以下の流れで治療が行われます。
- 単剤での治療から開始
- てんかん症候群の発作型に応じた薬剤選択
2.外科的治療
薬で効果が見られない場合、異常な組織の切除や神経の離断手術を行うことがあります。
主な手術
- 側頭葉てんかん:約80%で発作消失または改善
- 側頭葉外てんかん:約70%で発作消失または改善
- 迷走神経刺激療法(VNS):2年後までに平均50-60%の発作減少
3.その他
薬で効果が見られない場合、異常な組織の切除や神経の離断手術を行うことがあります。
- ケトン食療法
高脂肪・低炭水化物食の食事療法。偏った栄養バランスになるため、医師と栄養士の指導が必要。 - 迷走神経刺激療法
神経に電気的刺激を与える方法。補助療法としておこなわれる。
発作型、年齢、性別、副作用などを考慮して個別に、最適な治療法が選択されます。特に小児てんかんの場合、発作による発達の影響を考慮する必要があるため早期治療が大変重要とされています。
てんかん発作を誘発しやすい要因と気を付けると良いポイント
てんかん発作は、多くの場合突然起こりますが、特定の状況で発作のリスクが高まることがあります。発作の誘発要因を理解し、適切に対処することで、症状の管理に役立つ可能性があります。
① 体温の上昇、発熱
特に小児において、発熱は発作を引き起こしやすくする重要な要因の一つです。38度を超える発熱時には、早期に解熱剤の座薬を使用することが推奨されます。体温管理に注意を払い、感染症による発熱には迅速に対応することが大切です。
② ストレス、プレッシャーのかかる状況など
緊張や不安、興奮は発作のトリガーになることがあります。特に興味深いのは、緊張から解放され、一息ついた瞬間に発作が起こりやすいという点です。深呼吸や気持ちを落ち着かせる技術を身につけることで、発作のリスクを軽減できる可能性があります。
③ お薬の飲み忘れ
抗てんかん薬の服用は発作管理において最も重要な要素の一つです。処方された通りに服用し、飲み忘れた場合の対応について事前に医師や薬剤師に確認しておくことが重要です。
④ 光の刺激など、特定の刺激を長時間受ける
「テレビてんかん」と呼ばれる現象があり、特に光の点滅や特定の視覚的刺激が発作を誘発することがあります。テレビやゲームを見る際は、明るい部屋で適度な距離を保ち、長時間の視聴を避けることが推奨されます。
「チック」とは
チックとは、本人の意思に反して突発的に起こる素早い運動や発声を指します。主に4〜5歳ごろに発症することが多く、多くの場合は1年程度で自然に改善します。
症状としては、まばたき、顔をゆがめる、首を振るなどの運動チックや、咳払い、突然の声出しといった音声チックが挙げられます。症状の現れ方や経過は子どもによって異なりますが、成長とともに軽快するケースがほとんどです。
「チック」の原因は?
チックの根本的な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関わっていると考えられています。以下が主な要因です
- 脳内の神経伝達物質の異常
神経細胞間での情報伝達がうまくいかない場合があるとされています。 - 大脳基底核の機能障害
運動や行動の制御に関わる部分の影響が示唆されています。 - 遺伝的要因
家族内で似た症状が見られる場合もあります。 - ストレスや心理的要因
不安や緊張、疲労、興奮などが症状を悪化させる可能性があります。
チックの症状:タイプ別特徴
チックは、本人の意思とは無関係に突発的に現れる運動や発声の症状で、その変動性が特徴です。緊張時に症状が目立つ場合もあれば、リラックスした状況で増加する場合もあります。以下に、チックの種類について詳しく説明します。
① 運動チック
運動チックとは、身体の一部が不随意に動く症状を指します。以下のように単純運動チックと複雑運動チックに分類されます
- 単純運動チック
比較的簡単な動きが特徴で、以下の症状が含まれます:- まばたき
- 顔をしかめる
- 首を振る
- 肩をすくめる
- 複雑運動チック
より複雑な動作を伴うものが含まれます:- 顔の表情を変える
- 飛び跳ねる
- 地団太を踏む
- 特定の部位を繰り返し動かす
② 音声チック
音声チックとは、意図しない音や言葉を発する症状で、単純音声チックと複雑音声チックに分類されます
- 単純音声チック
簡単な音が中心で、以下のような例があります: - 複雑音声チック
意味のある言葉や反復的な言葉が含まれる場合もあります:
1年以上症状が続く場合:トゥレット症候群
運動チックと音声チックの両方が1年以上続く場合はトゥレット症候群と診断されることがあります。この症候群は、小児1,000人中3〜8人の割合で発生し、男性に多いとされています。症状が長期間続く場合には、専門医の診断を受けることが重要です。
チックの診断と治療法
チックの診断と治療は、子どもの生活の質を向上させるために重要です。チックの特性が見られたとしても自己判断せずに専門の医療機関を受診しましょう。
診断基準や治療方法を理解し、正しいアプローチを選択することで、子どもを適切に支えることができます。
チックの診断
チックの診断は、以下の基準を基に行われます
- DSM-5やICD-11(国際的な診断基準)を参照
- 医師による詳細な臨床評価
- 症状の持続期間(4週間以上)
- 発症年齢(18歳以下)
- 他の疾患との鑑別(トゥレット症候群ではない、ウイルス性脳炎などの医学的疾患ではない)
特に、専門医による正確な診断が不可欠です。自己判断は避け、医療機関での診断を受けることが推奨されます。
チックの治療法
治療の方針としては下記の流れで行われます。
- まずは非薬物療法から開始
- 症状が重度な場合や生活に支障がある場合は薬物療法を検討
- 必要に応じて複数の治療法を組み合わせる
非薬物療法
症状が比較的軽度の場合、以下の対応が基本となります
- 本人や家族へのチックの正しい理解の促進
- ストレス要因の軽減
- 規則正しい生活リズムの確立
またCBITという行動療法がおこなわれることもあります。以下のようなポイントで行動を変えてチックの軽減や解消を促します。
- 習慣逆転法(チックの代わりとなる新しい行動の習得)
- リラクゼーション法
- チックが起きる状況の特定と対処法の習得
薬物療法
行動療法ではうまく行かない場合や日常生活に支障が出たり自己評価が低下する場合は薬物療法がおこなわれることもあります。
歯ぎしりなどの場合はマウスピースをはめるなどで緩和される場合もあります。
チックがある子どもとの関わり方
チックは子ども自身ではコントロールできない症状であり、その特性を理解した上で、適切な対応をすることが大切です。周囲の大人がどのように接するかによって、子どものストレスが軽減され、安心して過ごせる環境を作ることができます。ここでは、チックがある子どもとの接し方のポイントをご紹介します。
① 症状が出ていることを責めたり怒ったりしない
チックは本人の意思とは無関係に起こる症状です。叱責は逆効果となり、子どものストレスを増加させる可能性があります。
穏やかに接し、子どもの存在をそのまま受け入れることが大切です。また、成長とともに多くの症状が軽減するため、親御さんが安心することも重要です。
② チックが悪化しやすい状況を把握する
チックはストレスや緊張、疲労により悪化する場合があります。日常生活を注意深く観察し、症状が増える場面を把握しましょう。
例えば、学校行事やテスト、人間関係の変化が影響することがあります。子どもと対話を重ね、どのような状況で症状が出やすいかを一緒に理解することが重要です。
③ ストレスの原因を取り除く
チックを引き起こす可能性があるストレス要因を特定し、できる限り軽減する努力が必要です。リラックス法や呼吸法を取り入れるほか、過度なプレッシャーや競争的な環境を和らげる工夫を行いましょう。
④ 幼稚園や保育園、学校などにも相談する
チックについて担任や養護教諭に相談し、教育機関と連携して子どもを支えることも大切です。いじめや偏見から守るため、クラス全体への啓発を行うことも効果的です。
学校側に「チックは本人の意思ではなく、不随意的な症状である」ことを説明し、柔軟な対応を依頼することで、子どもが安心して過ごせる環境を整えられます。
まとめ
「てんかん」や「チック」は、子どもの成長過程で見られることがある症状ですが、適切な理解と対応を行えば改善することも多いです。てんかんは正確な診断と治療により発作をコントロールできる場合が多く、チックもストレスの軽減や生活環境の調整によって軽快することが多いです。
親御さんが子どもの特性を受け入れ、焦らずに向き合う姿勢が、何よりもお子さまの安心感につながります。
専門家の意見を聞きながら、周囲の人の助けを借りて、お子さまが安心できる環境を作ってあげることが重要です。